高齢者が自立し豊かに生活を送っていくためには社会全体でサポートが必要です。核家族化した日本では以前のような家族介護だけでは限界があります。
利用者とサービス提供者の架け橋の役目でもある、ケアマネの仕事は今後も重宝される資格の一つ。その分必要な知識も幅広くケアマネジャー試験は難易度が高いとよく言われます。
特にこの数年でケアマネ試験はさらに難易度が高くなったと言われています。なぜそのように言われるのか実際のところの難易度はどうなのか、合格ラインや受験者数の推移などを見ながら、深掘りしていきます。
難易度の高いケアマネの合格を目指すなら
\ユーキャンがおすすめ/
ケアマネジャー試験の難易度や勉強時間
ケアマネ試験=難易度が高いイメージだけど、実際はどうなのかな
ケアマネ試験は合格率が低い、難易度が高いイメージがありますよね。
どれくらいの難易度なのか、対策方法などを知りたい方は、まずはどんな試験なのかを知るところから始めましょう。
ケアマネジャー(正式には介護支援専門員)試験は、実は国家資格ではなく、各自治体が扱う公的試資格です。
毎年1回、10月に行われ、各都道府県の大学などが試験会場となります。
受験する地域によって受験料や申し込み期間が異なるため注意が必要です。
またこれも意外と知られていないのですが、試験は自分で受験地を選べないので、こちらも注意が必要です。
原則、受験資格を満たしている業務で勤務している場合は勤務地の都道府県・勤務していない場合は居住する都道府県での受験となります。
ケアマネ試験について知って頂いたところで、難易度が高いイメージがなぜ付いているのか、ここからさらに深掘りしていきます。
ケアマネ試験の合格ライン
正解率70%が合格の目安
ケアマネ試験の合格ラインは正解率が約70%(その年の合格者数や難易度により合格ラインは補正されます。)
出題数は計60問で、以下のように大きく分けて2つの分野別になっています。
| 介護支援分野 | 介護保険制度について幅広く出題される | 25問 |
|---|---|---|
| 保健医療福祉サービス分野 | 高齢者の疾病を中心の医療についてや福祉サービスの詳細が出題される | 35問 |
また介護支援分野、保健医療福祉サービス分野、共に合格点に達していないと不合格になってしまいます。
バランスよく知識を求められているため、難易度が高いでしょう。
この問題数で正解率70%とはどれくらい?参考までに東京都の過去5年間の合格基準を見てみましょう。
| 分野 | 問題数 | 合格点 | |
|---|---|---|---|
| 平成29年度(第20回) | 1.介護支援分野 | 25問 | 15点 |
| 2.保健医療福祉サービス | 35問 | 23点 | |
| 平成30年度(第21回) | 1.介護支援分野 | 25問 | 13点 |
| 2.保健医療福祉サービス | 35問 | 22点 | |
| 令和元年度(第22回) | 1.介護支援分野 | 25問 | 16点 |
| 2.保健医療福祉サービス | 35問 | 25点 | |
| 令和2年度(第23回) | 1.介護支援分野 | 25問 | 13点 |
| 2.保健医療福祉サービス | 35問 | 22点 | |
| 令和3年度(第24回) | 1.介護支援分野 | 25問 | 14点 |
| 2.保健医療福祉サービス | 35問 | 25点 |
(注意) 配点は1問1点である。介護支援分野・保健医療福祉サービスごとに正答率70%を基準とし、問題の難易度で補正した。
「ケアマネ試験の合格率」については、こちらの記事を参照
解答方式の難易度
5肢複択方式が難易度が高い理由
出題形式は5肢複択方式(5つの選択肢から正しいものを2つまたは3つ選ぶマークシート方式)のことです。
しっかり学習して理解していないと正解にならないため難易度が高いでしょう。
ケアマネの仕事には専門的な知識が必要されることはいうまでもありませんが、その他にも社会への視野を広げ高齢者の気持ちを理解する気配りも大切になります。
そのため出題範囲もひろく問題数が多いのが特徴です。
試験時間は120分で合計60問を解答するわけですから、単純に1問にかけられる時間は2分ということになります。
この2分はぎりぎり使用した場合の時間。解答の見直しやマークミスなど間違いがないかチェックも必要ですから実際にはもっと少ないでしょう。
一見、試験時間が長いように思えますが実際は時間が足りなく感じるでしょう。
受験資格の厳格化
2018年度から受験者数が減ったから
過去7年分の受験者数を見てみると
- 2015年度(第18回)134,539人
- 2016年度(第19回)124,585人
- 2017年度(第20回)131,560人
- 2018年度(第21回)49,332人
- 2019年度(第22回)41,049人
- 2020年度(第23回)46,415人
- 2021年度(第24回)54,290人
2018年度から急激に減っているのが分かります。
これは、ケアマネの育成と活躍を目的に2015年2月に受験資格が見直され、介護等業務で実務経験を満たして受験する制度が廃止になったことが要因です。
(2017年の試験までは経過措置として改正前の受験資格が適用されていました。)
2018年より経過措置も終了し現在のケアマネジャー試験の受験資格は、国家資格等に基づく業務経験5年または相談援助業務経験5年のどちらかを満たす必要があります。
| ①国家資格等に基づく業務 | 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師、きゅう師・柔道整復師・栄養士・管理栄養士・精神保健福祉士 |
| ②相談援助業務 | 生活相談員(特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護・介護老人福祉施設・介護予防特定施設入居者生活介護などにおける生活相談としての業務)
支援相談員(介護老人保健施設の支援相談員としての業務) 相談支援専門員(計画相談支援、障害児相談支援における相談支援専門員としての業務) 主任相談支援員(生活困窮者自立相談支援事業などにおける主任相談支援員としての業務) |
①のみまたは②のみ、もしくは①②合わせて5年以上かつ900日以上の実務経験を満たしている人が試験を受けることができます。
このため、働きながら資格取得を目指す人が多くなり、勉強時間の確保が難しいため、ここ最近さらに難易度が高くなったと言われる要因でしょう。
逆に言えば既に受験資格がクリアしていれば、実はチャレンジしやすい試験といえるでしょう。
ケアマネの勉強はいつから始めるのがおすすめか
ケアマネの勉強はとにかく早く始めればいい?
受験資格が規定の国家資格または相談業務に関する5年以上の実務経験が必須になった今、この条件を満たすために働きながら資格取得を目指す人が多くなっていると先程述べました。
さらに家事や子育て中、ご家族の介護をしながら合格を目指している受験者も多くいるため十分な勉強時間の確保が難しい点が難易度を高くしている要因の一つでしょう。
そこで、みなさん共通して言えるのが、限られたスキマ時間をつかって効率的に勉強をすすめていきたい!!ですよね。
ケアマネ試験は毎年1回、10月に行われます。資格取得を目指す事を決めた時に、まずゴール地点を確認してからスタートしましょう。
そして最初に、過去問を一通り解いてみてください。今は解けなくても、間違っている箇所がたくさんあっても大丈夫です。
だってこれから勉強するわけですから、その時解けないのは当たり前!試験当日にこれらの問題が解ける自分になればいいのです。
ゴールしている自分をイメージしてスタート時点に立つ。これが大きな一歩です。
次に始める時期ですが、通学講座や通信講座を利用して学ぶ方は、各社それぞれのスタート時点に合わせればいいですが、独学の場合は自由にご自身で選べます。
出題範囲も広いし難易度が高いと言われるケアマネの試験。とにかく早めから勉強をすればいいと思いがちですが、そこには大きな落とし穴があるのです。
とにかく早めから勉強をすればいい!の落とし穴
- せっかく覚えたのに改定により内容が大きく変わるケースもある。
- 長すぎる勉強期間は、集中力の維持が難しい。
- 単純に途中で勉強に飽きる。
- 最初の方に覚えた内容を忘れる。
上記で述べた事を踏まえておすすめするスタートする時期ですが、6カ月から8ケ月前がおすすめです。
年度末の3月はご自身の職場で異動があったり、お子さんの卒園、卒業、春休みなど何かと忙しい時期。無理をしていざ始めたけど勉強時間の確保が難しく早々に諦めてしまいがちです。
3月までに準備だけはしておいて、新年度から晴れやかな気持ちで、スタートするのもいいですね。
独学で合格を目指す方にとって特に重要なテキストや問題集。発売日は各社例年1月くらいです。
前年度の試験について対策されている内容なので最新の物を使用するのが合格するための絶対条件。
制度が改正された場合、新しく導入された制度については出題されやすい傾向があります。なるべく早く始めたい方でも、このテキストや問題集が発売になってからがいいでしょう。
難易度の高いケアマネの合格を目指すなら
\ユーキャンがおすすめ/
ケアマネ資格を取得するメリット
難易度が高い試験を頑張るだけのメリットってあるのかな
ケアマネになったら、高齢者の生活をサポートしていく、やりがいある日々が待っています。
でも正直それだけなら今でも十分やりがいあるし。わざわざ難易度が高い試験を受けなくても。と思う方もいるでしょう。
ここからはケアマネになってからのメリットを4つにまとめてご紹介していきます。メリットが明確になっていると勉強を継続させるモチベーション維持にもつながりますよね。
- キャリアアップに繋がる
- ワークライフバランスが取れやすい
- 給料アップが期待出来る
- ケアマネ資格は将来性が見込める
以下で具体的にお伝えします。
1.キャリアアップに繋がる
ケアマネの資格を取得後、専門知識や技能が身に付き、今までの資格と合わせて理解できることが増えたなどの声もよく聞きます。
あわててケアマネのお仕事につかなくても、現在のお仕事にも活かせるということですね。
またケアマネには、5年ごとに更新があります。
合格してからも、常に勉強をする生活を保つことにより、時間管理能力や自己管理能力が向上し、お仕事以外の趣味の時間なども充実するでしょう。
難易度が高いと言われる資格をとることでご自身の自信へと繋がります。就職活動における自らの立場が優位になるため、「いつでも転職してもいいし」と気持ちが楽になり、日々抱えがちなストレスも減ります。
ケアマネの実務経験を重ねた先には、近年注目されているケアマネの上位資格にあたる主任ケアマネを目指すことも出来ます。
主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)とは、ケアマネの資質や専門性の向上を目的に2006年に創設されました。
主任ケアマネは新人をはじめとする他のケアマネの支援・指導・育成・相談対応などを担うまとめ役。
また介護・医療・福祉等の様々なサービスを適切に提供するためのネットワークの構築や地域包括システムの取り組みにも貢献することができます。
2021年3月に改訂された介護保険法では、居宅介護支援事務所の管理者は主任ケアマネジャーでなければならないとされました。
このことから、さらに需要が高まっています。
名刺などに「主任ケアマネジャー」と書いてあるとそれだけでキャリアの高さを認識してもらえ、今後仕事をしていくうえで、選択肢が増えることになります。
2.ワークライフバランスが取れやすい
介護のお仕事によくある悩みの、仕事と生活の両立が困難なこと。
実は他の医療関係や介護関係のお仕事に比べると勤務時間にメリットが。
平日の日勤が基本で、夜勤や宿直を担当することはあまりありません。
もちろん中にはシフト制で管理している事業者もありますが、ご家族の予定に合わせやすい勤務条件の求人も多くあります。
また正社員としてだけではなくフリーランスやパートなどで働くこともできるため年齢を重ねても働き続けることができるでしょう。
参考までに、令和3年の就業者統計データによるとケアマネの年齢は全国で50.9歳。東京都51.5歳、大阪府50.8歳でした。
3.給料アップが期待できる
気になる給与についてですが、ケアマネ経験年数と持っている他の資格が評価されて一般的な介護職員に比べてその平均給与は高く設定されています。
収入を上げられるのは難易度が高い試験を突破した資格があるこその強みでしょう。
いよいよ迫っている2025年問題。超高齢化社会によって医療や介護の需要と供給のバランスの崩壊が懸念されています。
ケアマネの活躍がさらに期待されている為、給与アップは期待できます。
令和3年の就業者統計データによると年収は全国では409.7万円、東京都454.3万円、大阪府409.9万円でした。
4.ケアマネ資格は将来性が見込める
高齢者やその家族にとって、介護制度は複雑に感じられることが少なくない。
これからますます加速していく高齢化社会のなかで豊富な知識を持つケアマネの需要が多くなるのは必至。
介護のAI化などのニュースも耳にするが、ケアマネは人とサービスなどとの繋がりをサポートする仕事。
国は質向上のため主任ケアマネの設置や研修受講の強化など制度化しました。
難易度が高い試験ですが、何かと不安な世の中、少しでもご自身の武器を多く持っているのは将来必ず役に立ちます。
難易度の高いケアマネの合格を目指すなら
\ユーキャンがおすすめ/
初めての方向け!ケアマネ試験の合格対策ポイント
前回本領発揮できず今回が再チャレンジの方は、きっとご自身の不得意な分野も分かっていて、次こそは!!と対策も見えていると思いますが、初めての方は何もわからない状態で難易度が高い試験に挑戦するのは不安ですよね。
そんな方は、この4つをポイントにして勉強を進めてみてください。
初めてのケアマネ試験の合格対策ポイント
①各分野をバランス良く学習する
②用語を確実に理解する
③得点源となる問題は確実に正解出来るようにする
④過去問を活用する
①各分野をバランス良く学習する
ケアマネ試験は大きく分けて2つの分野から出題されます。
介護支援分野から25問・保健医療福祉サービス分野からは35問・計60問です。
共に合格点に達していないと不合格になってしまうことは先ほど述べました。
各分野で正答率70%ということは、介護支援分野で18点・保健医療福祉サービス分野で25点で合格ラインに入ります。
試験当日の天候や会場の雰囲気からくる緊張、体調不良により本調子で臨めるかわかりません。
難易度が高いケアマネ試験を確実に合格するには、各分野80%から90%の正答率が取れるように、バランスよく試験勉強へ取り組みましょう。
②用語を確実に理解する
ケアマネ試験の勉強を進めていく中で難しいと感じる理由がこの、わかりにくい言葉、読めない漢字が多い介護用語。
ここはわかりにくい→わかりやすいに変換して覚えましょう。やさしく言い換えてどの場面に必要な言葉なのかイメージしながら覚えるのがポイントです。
例えば「食札(しょくさつ)」
病院や施設で準備されている食事の横に置かれている小さなカードのことです。
利用者の名前と食事の総カロリーが書かれていたり減塩食と書かれたりします。
アレルギーをお持ちの方もいるため誤って配膳しないための工夫のひとつです。一般の人が聞いても分かりにくいですよね。
「食事カード」など誰でもわかりやすい、やさしい言葉に換えると覚えやすいです。
例えば「個食(こしょく)」
例えば、こしょく
一般的には「孤食」と「個食」が使われていますが介護用語では「個食」といって個人の都合に合わせた食事という意味で使われます。
このようにただ暗記するのではなく、言い換えやイメージで1日に1用語覚えていきましょう。
ここをクリアにしておくとテキストや問題集を読むときの苦手意識が減りさらに理解度が上がります。
③得点源となる問題は確実に正解出来るようにする
ケアマネ試験は毎年、出題範囲も広いため勉強時間が足りないと焦ってしまう受験者が多くいます。でもテキストをすべて暗記する必要はありません。
約7割の正解で合格できるたケアマネ試験は、すべて完璧に覚えようとする勉強方法はおすすめしません。
それよりも落ち着いて問題文を読み解き確実に正解できるものを少しずつ増やしていきましょう。
例えばよくある問題文に「都道府県」が正しいところ「市町村」としていたり、「〇〇〇が(は)できない」など文末が同じ選択肢が並んでいます。
うっかり読み飛ばしたり読み間違えて違う選択肢を選んでしまうなどのミスは絶対避けたいです。
また毎年受験成功者を多く輩出したいと工夫され作られるテキスト。そこには毎年出る傾向の問題などが載っていますので、そこは重点的に覚えて確実に点を取りたいですね。
SNSで試験を終えた受験生のコメントを見てみると、「テキストにここは出るってなってたけどその通りだった」や「もっとここを重点的に勉強しておけばよかった」などを見かけます。
Twitterなどで生の声を見てみるのもおすすめです。最近ではYouTubeで学ぶ人などもいて、得点源を確実にする方法を知ることができるかもしれません。
④過去問題を活用する
ケアマネ試験は過去問を無料で見ることができます。
合格している人たちは過去問をとにかく解いたという声が多いです。
まずスタート時点で一通りやります。その際なるべく本番と同じ条件(時間など)でチャレンジすることをおすすめします。
そこで自身の現在の力を認識し、ご自身にとってどれくらいの難易度なのか、どの勉強方法で合格を目指すかなど、対策方法を考えることができます。
その後の勉強途中にも、定期的に過去問を解いていきましょう。前回よりも少しずつ正解が増えていくことで自信に繋げていきましょう。
もしも正解が増えていない場合は、勉強時間を増やすなどの検討をした方がいいでしょう。そこに早めに気付けることが重要です。
また分からなかった問題は当日中に解決しておくのも、難易度が高い試験に受かるための勉強法です。
ケアマネ試験合格のためのスクールや通信講座で学ぶ
独学でも合格は目指せますが、難易度が高いケアマネ試験を、より確実に狙うには通学講座や通信講座という選択肢もあります。
それぞれのメリット・デメリットがあるのでこちらで確認してご自身に合う方法を見つけてください。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 通学講座 |
|
|
| 通信講座 |
|
|
勉強を続けていくと、あれもこれもとテキストや問題集に目移りしたり、通学講座や通信講座など、他の方法がいいのではと不安になったりします。
でもそこは始めるときに決めた自分を信じてぐっと我慢!途中でコロコロやり方を変えるのは遠回りになる可能性があります。
そのため、どの勉強法を選ぶかは最初が肝心です。それぞれの特徴をしっかり見て自分に合うものを見つけてください。
ここで参考にして頂くために、おすすめの通信講座を一つご紹介していきます。
 引用元:ケアマネジャー資格取得講座|通信教育講座なら生涯学習のユーキャン (u-can.co.jp)
引用元:ケアマネジャー資格取得講座|通信教育講座なら生涯学習のユーキャン (u-can.co.jp)
創立1954年と歴史ある<生涯学習のユーキャン>は、人々の「向上心」「知的欲求」に応える様々ジャンルの学びコンテンツを提供しています。
その中でも気軽に始められる学びツールとして多くの受講者から高い評価を受ける通信講座。
約130もある講座では、年間約60万人の方が活用されています。その中でも人気のケアマネジャー講座は過去10年間で25,016名の合格者を輩出!
難易度が高い試験なのにこの合格者数は、驚きです!どのような内容なのか気になりますね。
| 講座名 | ケアマネジャー講座 |
| 標準学習期間 | 6ヶ月
|
| 教材 | メインテキストは全部で6冊 (介護保険制度論・介護支援サービス論・高齢者介護論Ⅰ・高齢者介護論Ⅱ・高齢者支援論Ⅰ・高齢者支援論Ⅱ) 副教材 (でるケアbest200・ガイドブック・過去問題集・資料集・添削関係書類・その他)特徴
|
| サポート体制 | 受講生限定のデジタル学習サイト(講義動画やwebテストをスマホやパソコンで学習できる)
|
| 金額(税込価格) | 一括払い・49,800円 分割払い・3,900円×13回(13ヶ月)総額50,700円 教育訓練給付金制度(一般教育訓練)対象講座 |
| 詳細 | 公式サイトはこちら |
(2022年8月23日現在)
独学に比べやはり費用の面が気になるところでしょうか。
分割払いもありますし、教育訓練給付金制度(一般教育訓練)を利用するのもいいですね。
この制度、よく見るけどイマイチわかっていないという方向けに詳細をご紹介していきます。
教育訓練給付金制度(一般教育訓練とは一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、支払った学費のうち20%(最大10万円)が支給される制度です。
実際どれくらい返ってくるのでしょうか。
ケアマネジャー講座の場合、一括払いで49,800円×20%=9,960円
支給額の算出元は設定学費ではなく支払済学費となります。
受験料もかかりますし、約一万円の返金はありがたいですね。
通信講座の魅力はやはり、毎年たくさんの合格者を輩出しているテキストやサポートの充実さ。
スマホやパソコンを利用したスキマ時間での学習が可能で自由度は高くマイペースに進められ、行き詰った時は質問が出来たり、自ら情報収集しなくても最新の情報が手に入る。
通学講座と独学の間?のようなイメージでしょうか?
もちろん費用のこともありますし、一概には言えませんが難易度が高い試験を確実に一発合格を狙うなら通信講座はおすすめです。
ユーキャン公式サイトにある「受講生の声」
合格の報告があった受講生の中から、特にお願いし取材にご協力いただいた方へのインタビューをまとめたものです。
実際受講された方々の体験談がとてもわかりやすい内容でした。いくつか見てみましょう。

法令が変わった場合は会報で教えてくれるのですが、有り難かったですね。以前は独学で勉強していたのですが、ちょうど法改正のあったときで、前例のない問題が出題されて…。それに対応しきれず、2回不合格してしまったんです。最新の情報が入手できるのは本当に助かりましたね。
添削課題ですね。合格できたのは、添削の先生方の温かい励ましの言葉があったからこそ。難しい問題が続き、つまずいているときは気分も落ち込みましたが、できない部分を的確に指摘するだけでなく、必ず思いやりのある励ましの言葉が添えられていました。
そのたびに「大丈夫、頑張ろう。私にもできる」とやる気を与えてもらいましたね。そのおかげで最後までくじけることなく勉強を続けられ、合格につながったのだと思います。
資格取得後は介護福祉士として現場の仕事も行いつつ、ケアマネジャーの業務も行うようになりました。この資格を取ることによって利用者さんをただお世話するだけでなく、より深く見る目ができたと思うので、本当に良かったです!引用元:ユーキャンのケアマネジャー資格取得講座|受講生の体験談 (u-can.co.jp)

はい。そのときにテキストが分かりやすかったことと、添削で先生の手書きメッセージが付いて戻ってくるのが嬉しく温かみを感じたので、今回も迷うことなくユーキャンで勉強しようと思いました。自分の経験から「ユーキャンなら大丈夫、安心だ」と思っていたので、他の勉強方法とは特に比較もしませんでしたね。
産休・育休の間にどうにかしたいという気持ちが強かったので、育児の合間に勉強していました。1日にだいたい2~3時間勉強していたと思います。
試験前の1ヵ月は過去問題など何度も問題を解いて、本番試験の時間配分をつかみました。 応用力をつけるために市販の問題集を購入することも考えましたが、結局ユーキャンの教材だけで試験に臨んで正解だったと思います。
試験問題の半分以上は、ユーキャンの教材にあった問題が出たと思います。けっこうスラスラ解けた印象があり、何問かだけ言い回しが難しい問題がありましたが、それ以外はユーキャンの教材でいつも解いていたものと変わらない感じを受けました。試験が終わった後は、だいたい大丈夫かなと80%の手応えを感じました。
私は一般病棟でヘルパーをしていますが、ケアマネの勉強の中には医療に関する分野もあったので、ナースが話している内容で分かることが増えました。ナースへの伝達がスムーズになり、患者さんの訴えを自分のところで処理できるようにもなってきましたね。
資格を取得できたことで、自分の気持ちがひとつ上になれたといいますか、「ちゃんと知識は持っているよ」という自信に繋がりましたし、周りの見る目も違ってきます。引用元:ユーキャンのケアマネジャー資格取得講座|受講生の体験談 (u-can.co.jp)

CMを見て知っていたことと、周囲にもユーキャンで受講してケアマネジャーに合格した先輩などがいたので、話を聞いていました。実際に受講して合格した先輩から「ユーキャン良かったよ」という話を聞いたのは大きかったですね。受講した人たちからとても評判が良くて、そこで私も資料請求してみて、受講期間が長く設定されていることに魅力を感じました。受験までサポートしてもらえるというのは、非常に心強かったです。
仕事のある日は、帰宅後に勉強しようと思っていても、あまりできないものなんですよね。だから休日に集中して勉強するスタイルでした。さすがに直前期は毎日のように勉強していましたが、気分が乗らない日や体調の悪い日は、休日と言えども全く勉強しないという日もありましたね。
それはもう、嬉しかったです! しかも、2つの分野で満点を取ることができました。最初の受験で合格できたので、達成感もありましたね。ケアマネジャー取得をきっかけに、障害者福祉施設から高齢者福祉施設に転職しました。
ケアマネジャーの資格があると転職に有利と言われますが、これは実際に転職を経験した私も実感しました。また、現場職で入社したとしても、ケアプラン評価やカンファレンスなどで知識を活かせるので、決して宝の持ち腐れにはなりません。
働きながらの勉強は本当に大変だと思いますが、ユーキャンのカリキュラムを信頼して頑張ってください。ユーキャンでケアマネの資格を取得していただきたいと思います。引用元:ユーキャンのケアマネジャー資格取得講座|受講生の体験談 (u-can.co.jp)

以前介護福祉士もユーキャンで勉強しました。
公式なテキストだけではポイントを絞っての勉強は大変でしたが、ユーキャンはある程度ポイントを絞って学習できる点がいいと思います。
ただ、基礎力DVDは失敗でした。講師の説明が最低!引用元:みん評


\過去10年間で25,016名の合格者を輩出!/
職場と相談して学習時間を設ける
時間は1日24時間しかありません。今でも十分忙しいみなさんにとって勉強時間を確保するには工夫と覚悟、そしてひとりで頑張りすぎない事が大切です。
今まで通勤途中にしていたゲームや動画再生の時間。
これと言って観たい番組があるわけじゃないのにダラダラ観ていたテレビの時間。
他にもスマホやパソコンで、検索するつもりがいつの間にかネットサーフィンをしていた時間。
これを全てとは言いませんが勉強時間にするだけでかなり違ってきます。
家事や子育て、介護などを他の家族に協力してもらったり、時短レシピに挑戦するのもおすすめです。
そして、どんなに工夫しても勉強時間が増やせない時は、一度職場の上司や先輩に相談することをおすすめします。
シフトの調整などで勉強時間の確保に協力してくれるかもしれませんし、現在ケアマネで活躍されている先輩がいたら、資格取得者のおすすめの勉強法などが聞けるかもしれません。
まとめ
超高齢化社会を迎える日本にとってケアマネジャーにはきわめて大きな役割を課せられています。
その分、求められることが多く、ケアマネ試験の難易度は高いのも事実です。
しかし、しっかり対策をしてご自身にあった勉強法で学習をすすめていけば合格も目指せます。
仕事や家事、子育てなどをしながらの勉強はとても大変です。時には家族や職場の方にも相談しながら無理なく続けることが大事です。
こちらでお伝えした内容が、これからケアマネジャーを目指される方の一助となれば幸いです。
難易度の高いケアマネの合格を目指すなら
\ユーキャンがおすすめ/
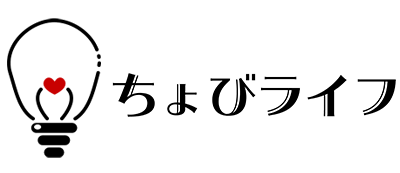
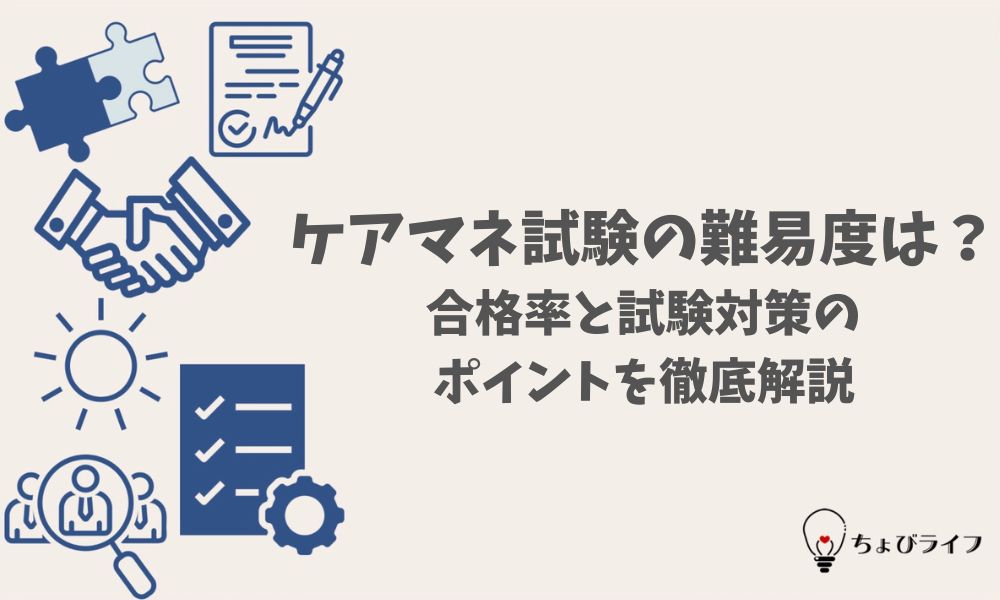
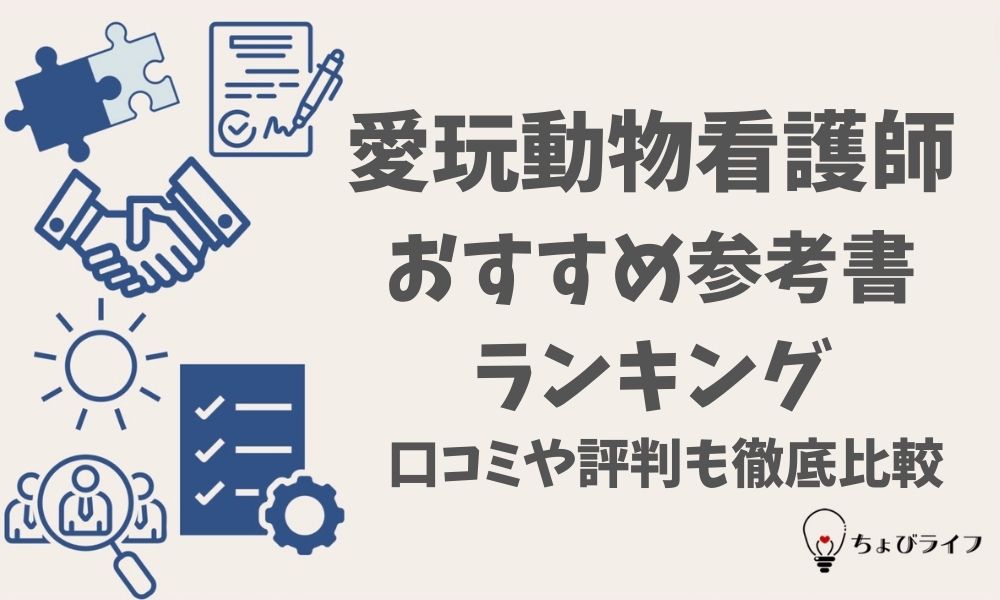
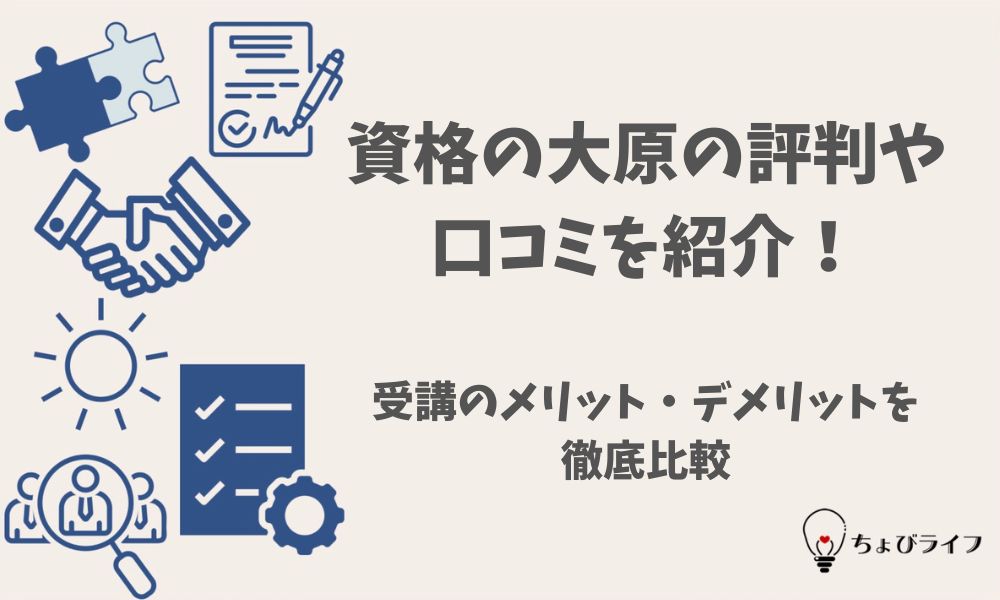

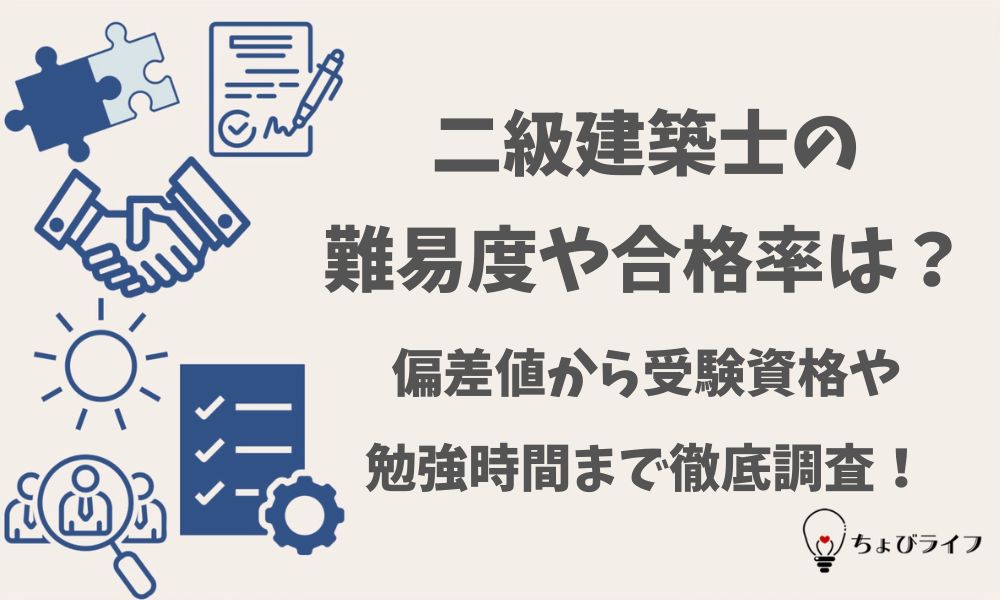
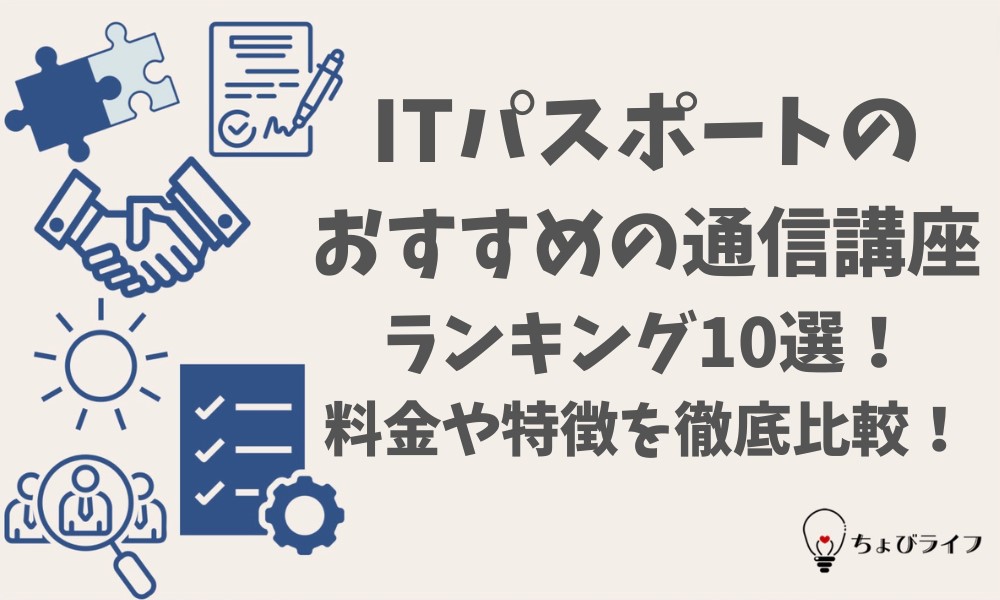
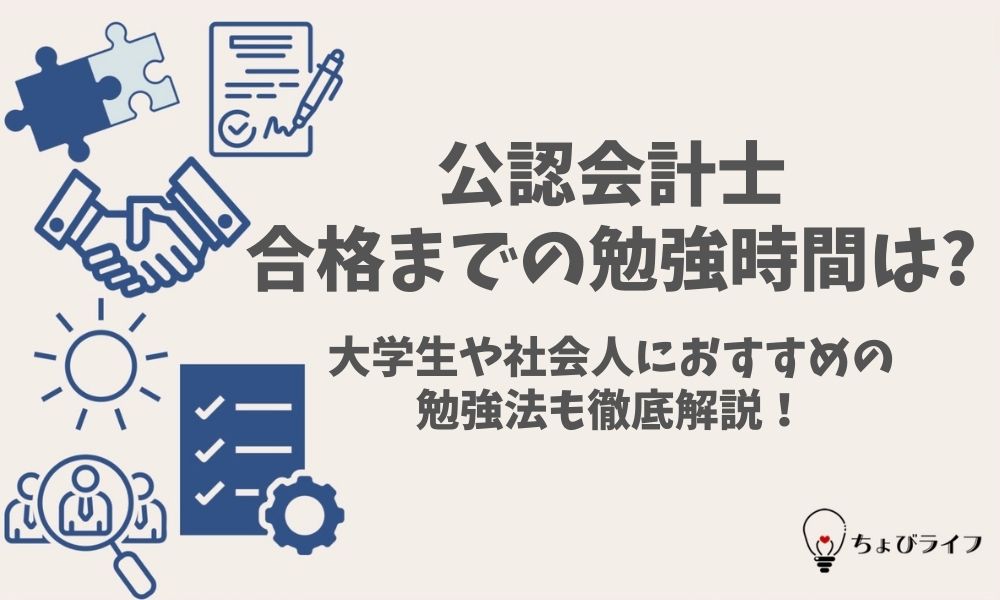
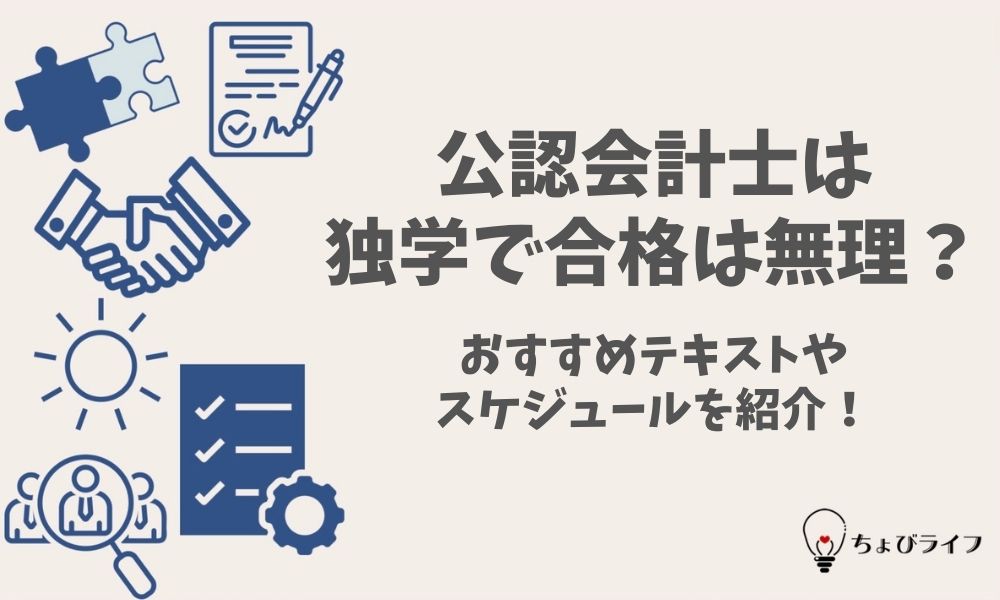
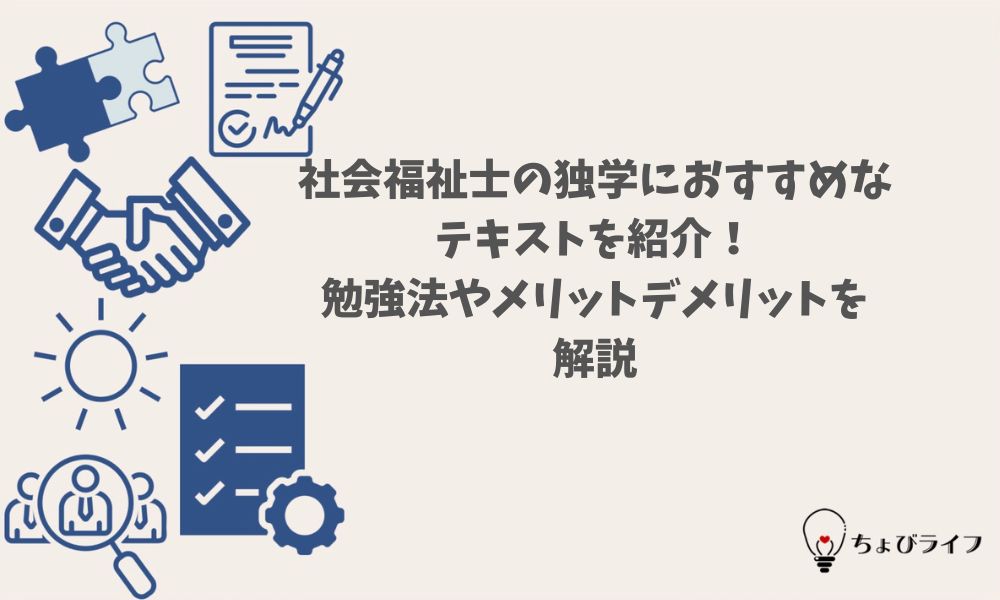
分かりやすい教材のようだ、というのが第一印象でした。ひとつの解答に対しても 「なぜその解答になるのか」という納得できる説明がなされていましたね。苦手だなと思う分野についても、納得しながら進めることができました。