社会福祉士とは、生活指導員・相談員・ソーシャルワーカー・ケースワーカーなど、福祉社会を支える専門職です。
高齢者や障害のある方など、福祉サービスを必要とする方の相談に応じ、助言や援助をするのが社会福祉士の役目です。
社会福祉士のニーズは拡大していますが、有資格者の数はまだ不足しています。
資格を取得し、キャリアアップや就職・転職に役立てましょう!
しかし、資格取得にあたって一番気になるところは試験の難易度ですよね。
今回は、社会福祉士になるための試験の内容や難易度について解説します。
一度取得すると生涯有効な社会福祉士の資格。ぜひトライしてみましょう!
\社会福祉士の資格取得を目指すなら通信講座がおすすめ/
社会福祉士の難易度は?

社会福祉士国家試験の難易度は比較的高く、一般的に難関資格と言われています。
その理由としては、受験資格が必要なことや、試験範囲が幅広いこと、合格基準が厳しいことなどがあげられます。
ここでは、社会福祉士の難易度が高い理由について解説していきます。
傾向やコツを掴むことができると充分合格が目指せます。
ぜひ最後まで読んでいただき、難関とされている社会福祉士国家試験の対策の参考になれば幸いです。
社会福祉士に必要な受験資格
社会福祉士の受験資格を得るためには、いくつかのルートがあります。
福祉系大学等または短大等に通い、指定の科目を履修して単位を取得している場合、また必要な実務経験を終えている場合はそのまま受験ができます。
そうでない方は養成施設に通い、受験資格を得ることが必要です。
また、福祉系大学・短大等で指定科目を履修して卒業した後には相談援助業務への従事が必要です。
福祉系大学・短大(指定科目履修)の場合、4年制の大学であればそのまま受験ができます。
3年制の場合は卒業後に相談援助の実務経験が1年必須、2年制の場合は卒業後に相談援助の実務経験が2年必須になります。
福祉系大学・短大(基礎科目履修)、4年制であれば短期養成施設などに6か月以上通うことが必要です。
3年制の場合は卒業後に相談援助の実務経験1年と、短期養成施設に6か月通うことが必要です。
2年制の場合は2年の実務経験が必要です。短期養成施設に通う期間は3年制の場合と同様、6か月です。
養成施設は、6月以上の短期養成施設等と、1年以上の一般養成施設等があります。
また、実務経験はどこで積めばいいか、ということが気になりますよね。
実務経験として認められる職種を一部挙げてみましょう。
児童分野
〇児童相談所…保育士、児童指導員、児童福祉士、児童心理士、相談員、心理判定員
〇児童養護施設 〇母子生活支援施設 〇知的障がい児施設 など
高齢者分野
〇介護保険施設…生活相談員、支援相談員
〇地域包括支援センター など
その他の分野
〇更生保護施設…補導主任、補導員
〇保健所…精神保健福祉士、精神保健福祉相談員 など
ルートは様々用意されていますが、受験資格を得るための時間と努力を考えても、社会福祉士は難易度が高い資格と言えます。
幅広い試験範囲
社会福祉士試験の出題範囲は広いです。
介護福祉士が13科目、精神保健福祉士が17科目に比べると、社会福祉士は19科目と一番多いです。
| 共通科目(科目数11) | ||||
| 人体の構造と機能及び疾病 | 7問 | |||
| 心理学理論と心理的支援 | 7問 | |||
| 社会理論と社会システム | 7問 | |||
| 現代社会と福祉 | 10問 | |||
| 地域福祉の理論と方法 | 10問 | |||
| 福祉行財政と福祉計画 | 7問 | |||
| 社会保障 | 7問 | |||
| 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 7問 | |||
| 低所得者に対する支援と生活保護制度 | 7問 | |||
| 保健医療サービス | 7問 | |||
| 権利擁護と成年後見制度 | 7問 | |||
| 専門科目(科目数8) | ||||
| 社会調査の基礎 | 7問 | |||
| 相談援助の基盤と専門職 | 7問 | |||
| 相談援助の理論と方法 | 21問 | |||
| 福祉サービスの組織と経営 | 7問 | |||
| 高齢者に対する支援と介護時保険制度 | 10問 | |||
| 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 7問 | |||
| 就労支援サービス | 4問 | |||
| 更生保護制度 | 4問 | |||
試験の中では専門用語や制度が登場するので、覚えておくことが必要です。
また、試験範囲が広いと苦手な科目が出てきてしまいます。
何から手をつけていいかわからず勉強方法を見つけることが難しかったり、モチベーションが下がることで勉強の意欲を維持できずに後回しにしてしまったりということになりかねません。
範囲が広いということは、自分に合った勉強方法で効率良く知識を身につけていくことが大切です。
厳しい合格ライン
社会福祉士試験に合格するには、問題の総得点の60%程度正答することが必要です。
また、問題の難易度で補正した点数以上の得点と、18科目全てで得点するという2つの基準を同時に満たすことが必要です。
しかし、試験科目の多さから勉強不足になってしまうことで、合格率が下がってしまうことに繋がります。
また、18科目全てで得点することが必要なので、得意科目ばかりを伸ばす勉強方法も正しいとは言えません。
専門用語が使われることが多く覚えるべきこともたくさんありますから、苦手な科目も効率よく勉強することで知識を入れておくことが必要です。
社会福祉士に合格するためには300時間の勉強が目安とされています。
大学や養成施設に通いながら、また働きながらだと勉強時間の確保が難しいですよね。
勉強時間を確保するために、1日の中でどのくらい勉強時間にあてられるかを考えて計画し、無理のないスケジュールでコツコツと知識を積み重ねましょう。
合格基準点は総得点の60%
総得点に対する合格ラインは毎年問題の難易度によって変動します。
約60%以上の正答率と18科目全てで1点以上得点することが必要です。
また合格ラインの目安は、1問1点で150点満点が総得点なので、90点の得点が必要になります。
そして0点科目があると即不合格になってしまうので、例えば70%をとっていても得点できなかった科目が1つでもあれば合格することはできません。
得意分野だけでなく苦手分野もまんべんなく勉強することが大事でしょう。
「上から何人が合格」という試験ではないので、慌てず自分に合った効率の良い勉強がしっかりできていれば、大いに合格に近付くことができます。
当日を良いコンディションで迎えられるよう、日々コツコツとした学習を積み重ねておきましょう。
18科目すべてで得点する
一度で18科目全てに合格しなければならないので、全科目に対する対策が必要です。
また配点の仕方は1問1点の150点満点です。
240分の中で150問を解答する必要があるので、時間配分に気を付けていきましょう。
試験はマークシートなので、塗り間違い防止のために最初から解いていくことが望ましいと言えます。
自信のない問題だったとしてもとりあえず「これだ!」と思うものを選び、マークシートを塗っておきましょう。
見直す時間がなかったとしても、とりあえず解答しておけば正答の可能性があります。
また、上記でも述べた通り0点科目があれば即不合格になってしまうので、得意科目で不得意科目をカバーするという特性が薄く、それが難易度に表れていると言えます。
自分用のまとめノートを作ったり、自己流の勉強に行き詰まるなら通信講座などを利用し、不得意科目を重点的に勉強する方法もいいでしょう。
社会福祉士の偏差値
社会福祉士の偏差値は57とされており、一般的に見ると普通のレベルと言えます。
しかし、難関資格と言われている「宅建士」57、「測量士」59などと並ぶ偏差値なので、簡単に合格することは難しいでしょう。
偏差値が77ほどの「司法書士試験」や「公認会計士試験」などの超難関の国家資格に比べると難易度は下がりますので、しっかり試験対策をして挑みましょう。
\社会福祉士の資格取得を目指すなら通信講座がおすすめ/
社会福祉士の合格率
社会福祉士を目指すと決めたら、一番気になるのが試験の難易度や合格率ですよね。
いったいどんな人が試験に合格しているのでしょうか。
社会福祉士の合格率は30%前後とされていて、比較的低い合格率となっています。
やはり難易度の高い資格と言えますが、実際の合格率がどのくらいなのか、色々な角度から検証してみましょう。
合格率の推移
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2021年度 | 35,287名 | 10,333名 | 29.3% |
| 2020年度 | 39,629名 | 11,612名 | 29.3% |
| 2019年度 | 41,639名 | 12,456名 | 29.9% |
| 2018年度 | 43,937名 | 13,288名 | 30.2% |
| 2017年度 | 45,849名 | 11,828名 | 25.8% |
(2022年8月28日現在)(厚生労働省調べ)
2017年度の受験者数は45,849名で、合格者数は11,828名になっています。合格率は25.8%です。
2021年度の受験者数は2017年度から比べると35,287名となっており、1,000名以上減少しています。
この表からわかるように、年々受験者数が減少していますが合格者、合格率はともに上がっています。
男女別の合格率
| 性別 | 合格者人数 | 合格率 |
| 男性 | 3,272名 | 30.5% |
| 女性 | 7,470名 | 69.5% |
(2022年8月28日現在)(2019年度試験厚生労働省調べ)
また、上の表からわかる通り女性の合格者割合が高くなっています。
これは、福祉業界全体の特徴と言えるようです。
受験資格別の合格率
| 区分 | 合格者数 | 合格率 | |
| 福祉系大学などの卒業者 | 7,232名 | 58.1% | |
| 養成施設卒業者 | 5,224名 | 41.9% | |
(2022年8月28日現在)(2019年度試験厚生労働省調べ)
合格者数全体に占める割合としては、合格率が58.1%の福祉系大学卒業者の方が多いです。
しかし2つの受験資格を比べてみても大きな差はなく、養成施設卒業者も合格率はそれほど低くはありません。
どちらのルートで勉強したとしても、社会福祉士国家試験の内容は変わりません。
目標を持ちしっかりと試験対策をし、合格を目指しましょう。
年代別の合格率
| 年齢区分 | 合格者数 | 合格率 |
| ~30 | 6,050名 | 48.6% |
| 31~40 | 2,439名 | 19.6% |
| 41~50 | 2,368名 | 19.0% |
| 51~60 | 1,269名 | 10.2% |
| 61~ | 330名 | 2.6% |
(2022年8月28日現在)(2019年度試験厚生労働省調べ)
表からわかる通り、30歳までに資格取得しようとする人が圧倒的に多い傾向です。
年齢制限はないため幅広い年代が受験しています。
また、新卒と既卒では合格率に大きな差があります。
2021年度の新卒の方たちの平均合格率は49.2%となっているのに対し、既卒の方たちの平均合格率は15.9%となっています。
大学や養成施設で学んだ知識を新鮮なままに受験した方たちが合格しやすいと言えるでしょう。
なぜ年代別に合格率が下がっていくかというと、やはり一度勉強から遠ざかってしまうことが原因と言えます。
環境が変わったり、働きながらだと充分な勉強時間が確保できなかったりモチベーションの維持も難しいでしょう。
しかし、既卒だからと望みが薄いわけではありません。
勉強の習慣化や、環境に影響されずコツコツと知識を積み上げることができれば合格を目指すことができます。
合格率の低い理由は?
社会福祉士国家試験は出題範囲が広く、また60%程度の正答率が求められます。
全ての科目で1点以上得点を取らなければならないので、全科目を勉強していないと合格は難しいです。
法律や制度を覚えることだけではなく、それに付随される歴史上の人物なども覚えなければなりません。
また、一度勉強した内容も復習をしなければ知識の定着は難しいでしょう。
範囲が広いということは次から次へ知識を入れなければならず、混乱を招いたり忘れてしまうことも大いにあり得ます。
独学だとどのようなテキストで勉強したらいいのかわからない、重要なポイントがつかめない、などの問題が出てきます。
次で述べるような問題も出てくるでしょう。
勉強時間の確保が難しい
社会福祉士の試験は科目数が多く、また全ての科目で1点以上の得点が必要です。
得意分野だけを伸ばしても良い対策とは言えず、苦手分野も克服しておくことが大切です。
しかし社会人は働きながら受験対策をするため、特に勉強不足になりがちです。
大学や養成施設に通っている時は試験勉強に専念する環境が整っていますが、働きながらだと、まず疲れから勉強に身が入らない場合があります。
計画的なスケジュールを立てることができる方はコツコツと勉強できますが、上記で述べた通り社会人で目指す方の大半は色々な弊害がありますね。
結果、受験までに勉強が足りず合格できないこともあるでしょう。
社会福祉士国家試験を目指すなら、勉強時間は300時間が目安とされています。
試験日に合わせて逆算し、苦手科目が多い場合は余裕を持って試験勉強を開始しましょう。
モチベーションの維持が困難
出題範囲が広い社会福祉士は長期的な勉強が必要になります。
大学や養成施設では仲間と競い合いながら切磋琢磨を続け、行き詰まった時や質問したい時にはすぐに聞きに行ける先生や講師がいます。
しかし社会人で働きながら自力で勉強するとなると、孤独で長い戦いになります。
また、家事や育児など勉強に専念できない環境で目指す場合もあるでしょう。
そういった場合はモチベーションが保てずにコツコツと勉強を積み重ねることが難しく、合格には厳しい状況になると思います。
孤独な戦いをしていると自分で勉強をしたところが最新のものなのかどうかわからなかったり、本当に正しい知識なのか質問することもできずに不安が増していくでしょう。
そのような状態では効率が良く質の良い勉強ができるとは言えません。
それゆえにモチベーションが維持できず、何年もかけて勉強したとしても合格は難しくなります。
メリハリのある計画的なスケジュールを立てたり、わかりやすくまとめられたテキストの活用や試験内容の傾向を掴むための過去問などで、効率良く勉強することが大切です。
自身の将来像をしっかりイメージし、何のために社会福祉士を取得するのかを今一度呼び起こしましょう。
強い意志をもって試験に挑むことが大切です。
\社会福祉士の資格取得を目指すなら通信講座がおすすめ/
社会福祉士の効率的な勉強方法

社会福祉士国家試験は出題範囲が広く簡単に合格することは難しいですが、ポイントを押さえて効率良く勉強することで、充分資格取得を目指すことができます。
しかしこれまで述べてきた通り、独学だと勉強時間の確保やモチベーションの維持が難しく、効率の良い勉強ができるかと言われると難しいでしょう。
ではどのように勉強をしていけばいいのか、ここでは社会福祉士国家試験の受験対策を始めようとしている方に向けて、効率の良い勉強方法を紹介していきます。
①計画的な学習スケジュールを組む
社会福祉士国家資格の試験に合格するためには、約300時間の勉強時間が必要と言われています。
実際に、300時間勉強するためのスケジュールの例を紹介します。
1日2時間 毎日勉強した場合
2時間×30日で60時間、300時間÷60時間で5か月
1日2時間 週5日勉強した場合
2時間×5日×4週で40時間、300時間÷40時間で7.5か月
1日1時間 毎日勉強した場合
1時間×30日で30時間、300時間÷30時間で10日か月
社会福祉士の試験は1年に1度です。計画的に勉強し、1年に1度のチャンスを掴みましょう。
しかし、ただノートに書き写したり、問題を解いていくだけでは知識の定着は難しいでしょう。
知識を積み重ねるためにはテキストを読んで知識を得て暗記するなどのインプットと、蓄えた知識を使って問題を解いたり理解した内容を復習したり他者と共有するなどのアウトプットが大切です。
また、勉強時間の確保が難しいからと言って休みの日にまとめて勉強をしても、勉強内容をずっと覚えておくことは難しいです。
そこで大切なのが、復習です。
毎日コツコツ隙間時間などを利用して勉強した内容を、まずは勉強の最初に復習しましょう。
どこまで覚えているのかがわかり自身に繋がりますし、より知識の定着が図れるでしょう。
②時間を効率的に使う
大学に在籍して環境が整っていれば勉強時間を確実に確保することができるでしょう。
しかし社会人は働きながら勉強時間を確保することがとても難しいです。
残業などがありまとまった勉強時間が確保できず、休みの日などにまとめて勉強するしかなくなってしまいます。
自分の自由時間がなくなり、モチベーションの維持が途端に難しくなるでしょう。
自己流の勉強が難しい場合は、通信講座を利用することが有効的と言えます。
決められたスケジュールやカリキュラムで進められる通信講座の力を借りることで、モチベーションを維持しつつ、効率的に合格ラインの60%に狙いを定めた勉強を行うことができるでしょう。
テキスト学習のインプットと、問題を解くアウトプットを繰り返すことで、知識が定着していきます。
また、ペンやノートを使って書くことだけに集中してしまうと、勉強をしたつもりになっているだけで実は時間をロスしている…なんてことになりかねません。
自分の苦手な科目についてはノートに書いて理解を進めていくことが必要かと思いますが、得意な科目については既にわかりやすくまとめられたテキストを利用しましょう。
③過去問を活用する
合格を目指すなら、まずは過去問に手をつけましょう。
これまでの問題の傾向や雰囲気を掴むためにも、模擬試験を解いてみるのもおすすめです。
本番の試験時間に合わせて模擬試験を解くことで、自分のペースを掴んでいきましょう。
また、福祉分野はその時の社会情勢で法律が変わるので、過去問で出題傾向や雰囲気を掴みながら最新のテキストも使いましょう。
社会福祉士の効率的な勉強方法
①計画的な学習スケジュールを組む
②時間を効率的に使う
③過去問を活用する
効率的な勉強方法が難しいと感じたら通信講座を活用することがおすすめです。
通信講座を利用すると3年分の過去問が収録されており、どれから手をつけていいのかと迷うことなく出題傾向や解答のコツを掴むことができるでしょう。
隙間時間にはスマホで勉強し、わからないことがあればメールで気軽に質問ができます。
隙間時間を利用し、無理なく効率良く勉強しましょう。
社会福祉士におすすめの通信講座
 引用元:社会福祉士資格取得講座|通信教育講座なら生涯学習のユーキャン (u-can.co.jp)
引用元:社会福祉士資格取得講座|通信教育講座なら生涯学習のユーキャン (u-can.co.jp)
難易度の高い社会福祉士試験の勉強には、ユーキャンの通信講座をお勧めします。
独学でも合格を目指すことはできますが、より効率良く勉強をするならユーキャンのわかりやすくまとめられたテキストを参考にし、計画的に決められたカリキュラム中で進めていく方法がいいでしょう。
独学に向いている人
〇勉強のスケジュールを計画的に立て、実行できる人
〇環境に影響されず、強い意志を持ってコツコツと勉強を積み上げられる人
〇頑張る時と休む時のメリハリをつけられる人
〇自分の得意や苦手を把握し、効率良く勉強できる人
このように、徹底した自己管理ができる方は独学でも充分に合格を目指せるかと思いますが、特に社会人など働きながらの環境に置かれている方はとても難しいと思います。
また、新しい情報を手に入れることが難しいということや、自分の知識がどこまでついたかわかりにくいという問題や、孤独がゆえにモチベーションの維持が難しいという問題が出てくるでしょう。
そこで、ユーキャンの通信講座を利用するメリットをお伝えします。
ユーキャンの通信講座を利用するメリット
- 試験を熟知した講師たちによって作成された、内容に無駄のない教材が届く
- 決められたカリキュラムで効率良く試験勉強ができる
- 質問したい時にスマホからすぐに質問ができるという安心体制
- 3年分の過去問で試験の傾向が掴める
- 2004年から2020年までに7,307名の合格者が出ているという実績がある
範囲の広い社会福祉士の勉強のために、自分で教材選びや勉強スケジュールを立てるには限界があるかと思います。
しかし、ユーキャンの通信講座を利用するとより合格に近付くために寄り添ったサポートをしてくれます。
上記で述べたメリットだけではなく、他にも全部で6回の添削課題が用意されます。
提出した課題には丁寧なアドバイスをもらうことができるので、確実に力がついているという実感が持て、自信に繋がります。
ぜひユーキャンの通信講座を利用し心強さを感じながら、安心して勉強をしていきましょう!
わかりやすいテキストが評判
\信頼と実績の通信講座/
社会福祉士の通信講座のメリット・デメリットについてはこちらで詳しく紹介しています!
社会福祉士と他資格の難易度を比較
福祉分野にはたくさんの資格があります。
それぞれの資格は支援対象者が異なり、仕事内容も大きく変わってきます。
どの資格も困っている方や支援の必要な方の役に立ち、他者貢献ができているという達成感や喜びに繋がるでしょう。
これから、他資格に比べると社会福祉士の難易度がどのくらいなのかを比較していきましょう。
介護福祉士
会議福祉士は障害があったり、介護の必要がある高齢者が支援対象です。
介護福祉士より社会福祉士の方が支援の対象者が多いため覚える知識や技術は多いですが、介護福祉士は身体介護や生活援助が主な仕事なので、より実践的と言えます。
資格の取り方にも違いがあります。
介護福祉士は実務者研修を終えてから3年以上の実務経験を積むことや、養成学校でカリキュラムをこなすということがメジャーです。
介護福祉士の合格率は60%から70%で、出題範囲も主に介護関連の内容に限られています。
社会福祉士の方が福祉関係全般と出題範囲は広いため、勉強する大変さで言えば資格取得の難しさがあるかもしれません。
また試験時間は社会福祉士が240分に対して、介護福祉士は220分です。集中力の持続が大切です。
ケアマネージャー
ケアマネージャーは社会福祉士と同様福祉分野の資格ですが、仕事内容は大きく異なります。
まず、社会福祉士が国家資格なのに対し、ケアマネージャーは国家資格ではありません。
略してケアマネと呼ばれたり、介護支援専門員とも呼ばれます。
いわゆる介護のプロとされています。
社会福祉士とケアマネージャーの仕事内容は異なりますが、2つの職種で連携することが多いです。
ケアマネージャーが支援計画を立て、社会福祉士が関係機関との連携役になります。
そんな2つの資格を試験の難易度で比べると、合格率はケアマネージャーが20%程度、社会福祉士が30%弱となっています。
数字だけを見るとケアマネージャーの方が難易度は高いですが、ケアマネージャーは介護福祉士などの国家資格を持ち、5年以上の実務経験が必要という受験の条件があります。
なので、一概に難易度を比べることはできないでしょう。
ちなみに試験時間を比較すると、ケアマネージャーが120分に対して社会福祉士は240分です。
合格率で比べた場合には、社会福祉士の方が資格取得しやすいかもしれません。
精神保健福祉士
社会福祉士の支援対象は高齢者、障害者、虐待を受けている子どもなどに対し、精神保健福祉士の支援対象はうつ病、統合失調症など、精神疾患を持っている方たちになります。
そういった方たちの相談を受け、社会復帰の手助けや生活支援などをしています。
どちらの仕事も福祉支援ですが、支援対象が異なることから仕事の内容も全く変わってくるということがわかりますね。
また精神保健福祉士も社会福祉士と同様に、国家試験を受ける際には大学や養成施設を出ていることが受験の条件となっています。
そんな精神保健福祉士の合格率は60%程度と、社会福祉士の30%弱に比べると高くなっています。
出題範囲も精神保健福祉士は「精神医学、精神保健学」など精神保健福祉士に特化していて社会福祉士よりも狭くなっています。
精神保健福祉士の方が対策しやすいかもしれません。
しかし社会福祉士試験は240分で1日で終了しますが、精神保健福祉士試験は275分で2日必要になります。
また会場も社会福祉士試験の方が多く、お住まいの地域によっては精神保健福祉士の方が受験しにくいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
\社会福祉士の資格取得を目指すなら通信講座がおすすめ/
まとめ
社会福祉士試験で合格するためには、満点をとる必要はありません。
合格基準である「総得点150点に対し60%程度の正答(難易度により補正される)、18科目群全てで最低1問は正答」をクリアすればいいのです。
どの科目もまんべんなく点数がとれるよう、時間内に全ての問題を解けるよう時間配分することが大切です。
計画的にスケジュールを立てて勉強することができれば、独学でも合格を目指すことができるでしょう。
過去問を解き、毎日コツコツ勉強し復習を重ねることが大切です。
しかし、より確実に合格を目指すなら通信講座がおすすめです!
出題されやすい問題のポイントに絞って作られたテキストや、決められたスケジュールに沿って勉強することで効率良く合格が目指せるでしょう。
また、添削や質疑応答にも対応してくれるので、苦手を克服し確実に力を伸ばしていけます。
難関と言われている社会福祉士国家資格の試験ですが、寄り添ったサポートをしてくれる心強いユーキャンの通信講座を利用し、傾向を掴み対策を立てましょう。
ぜひ、社会福祉士への第一歩を踏み出してみましょう!応援しています。
\社会福祉士の資格取得を目指すなら通信講座がおすすめ/
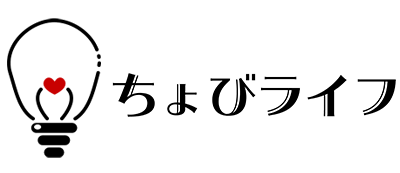
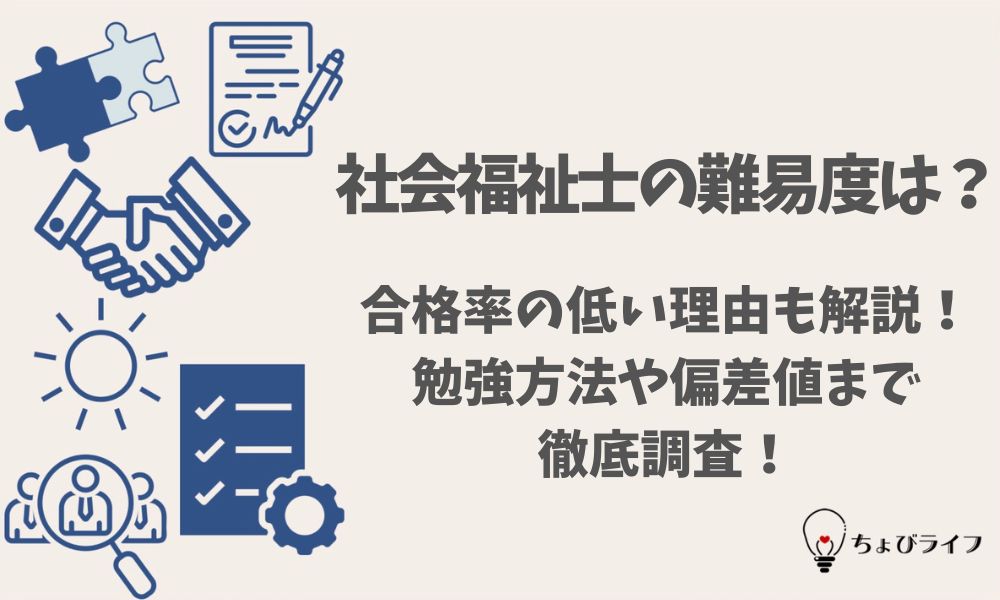
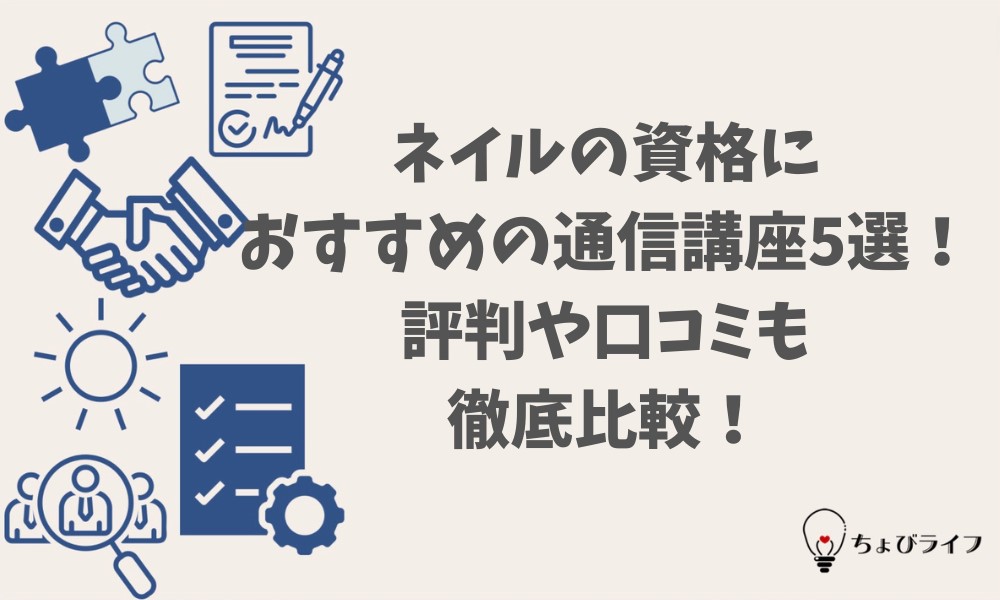
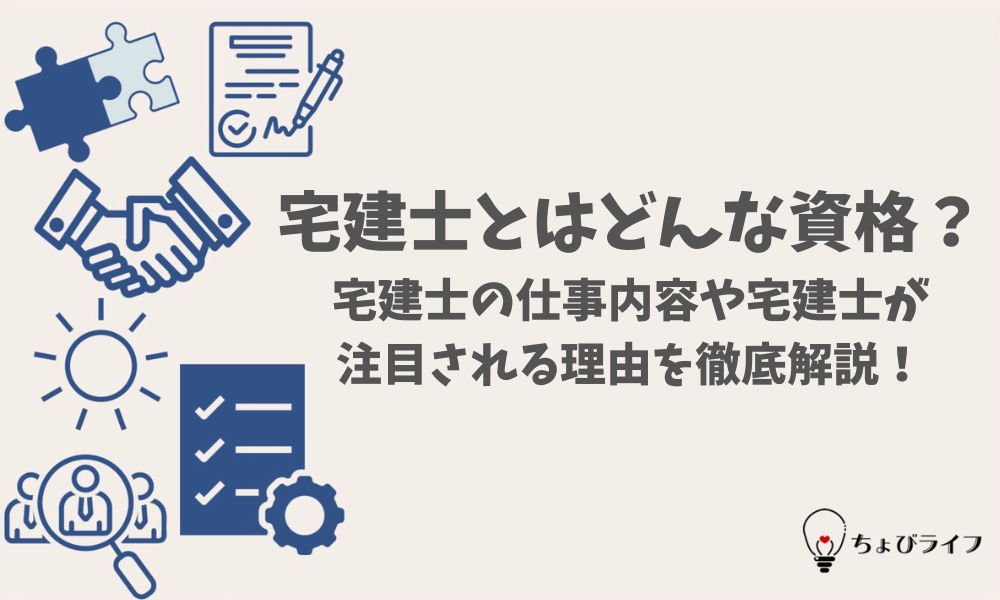
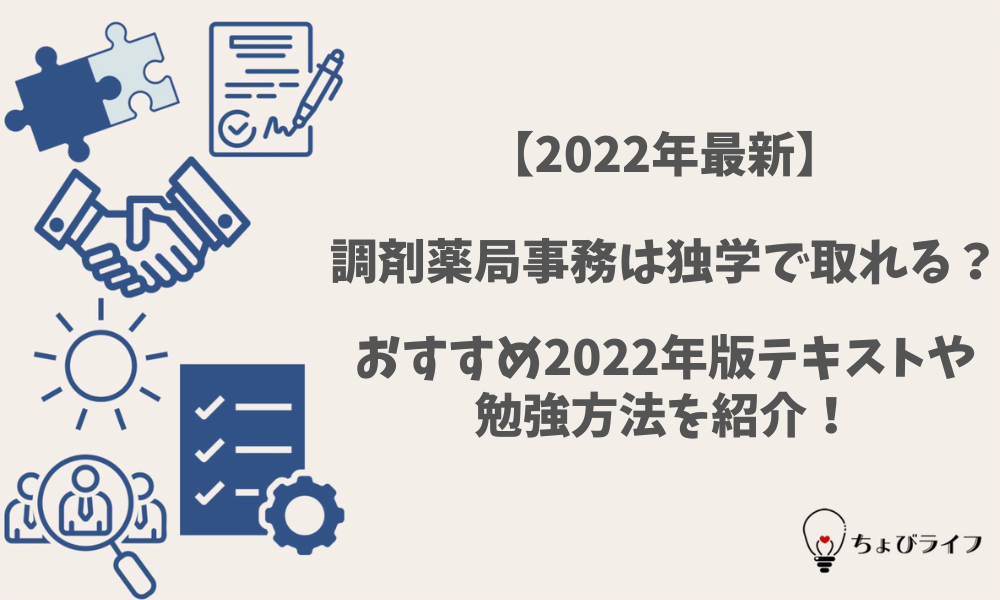
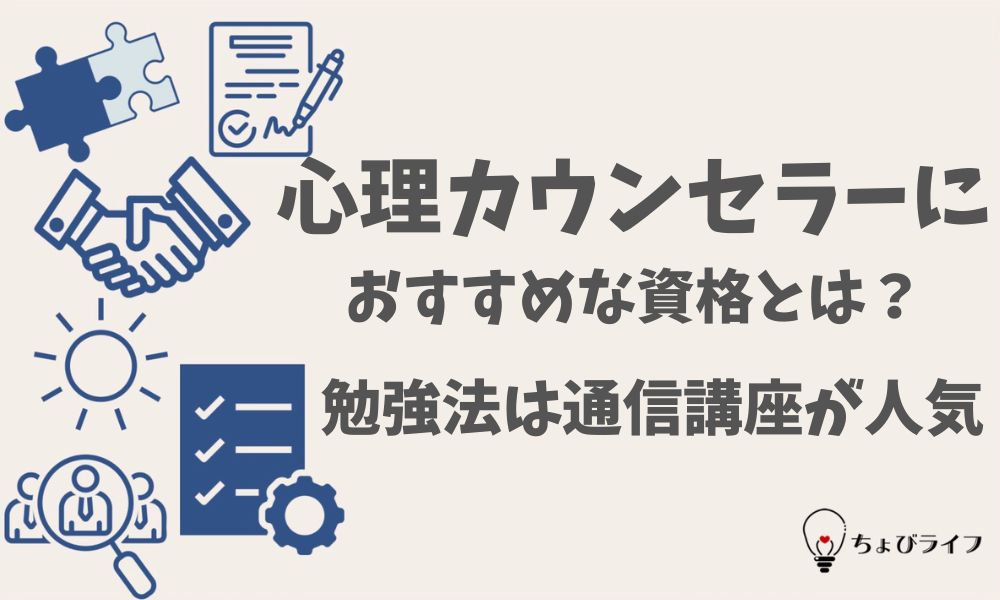
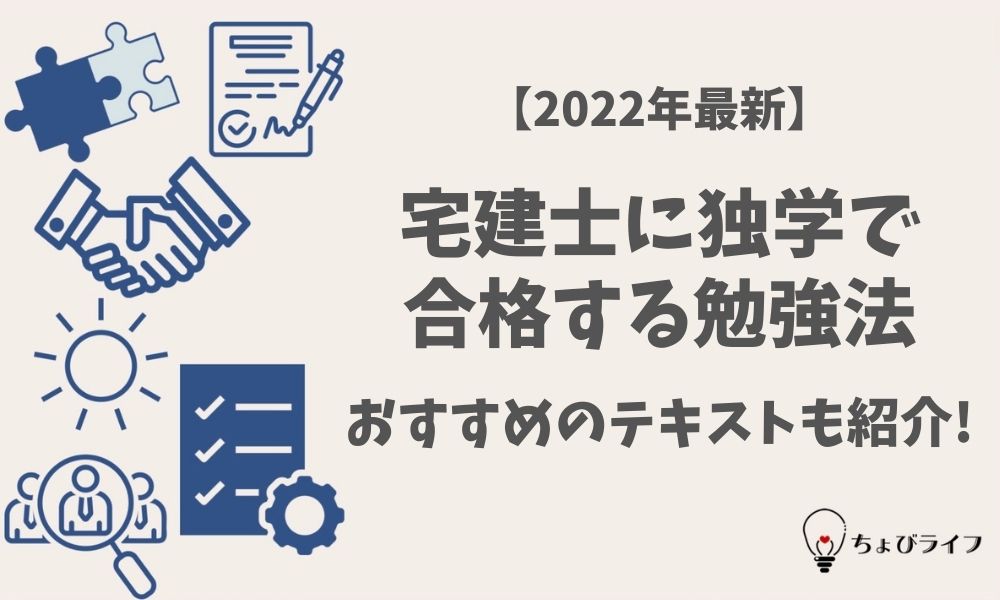
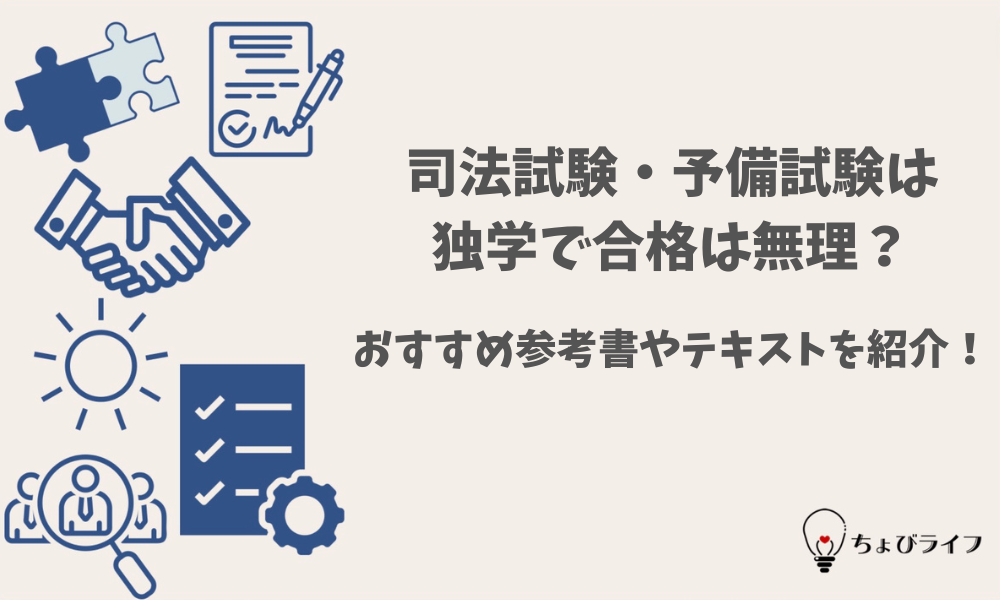
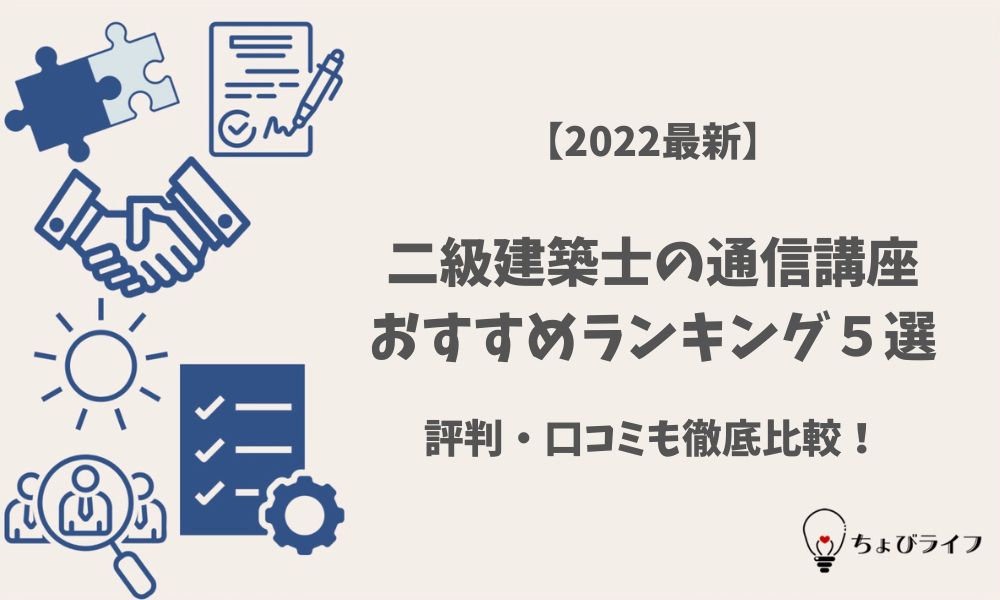
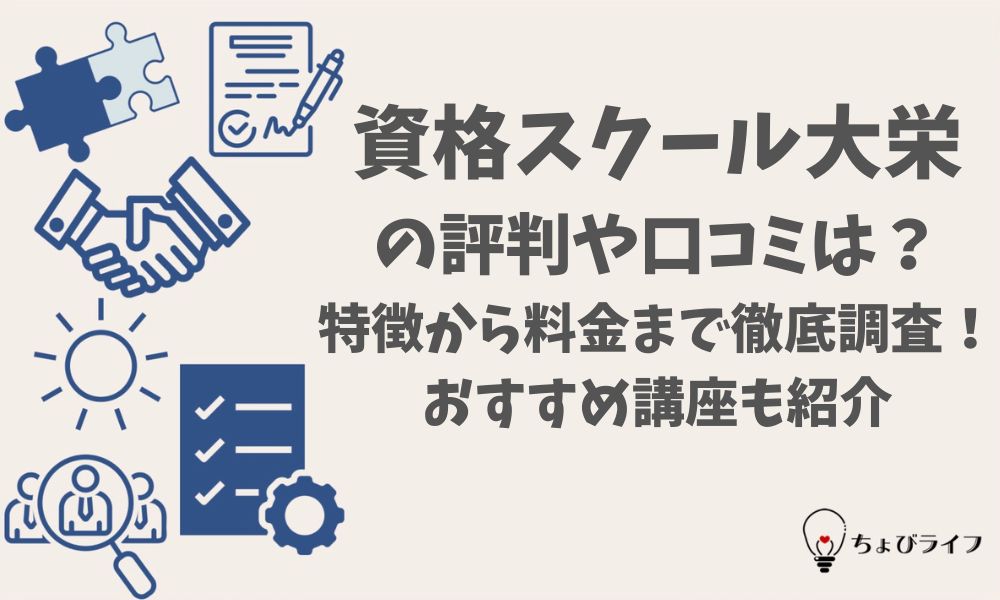
コメント