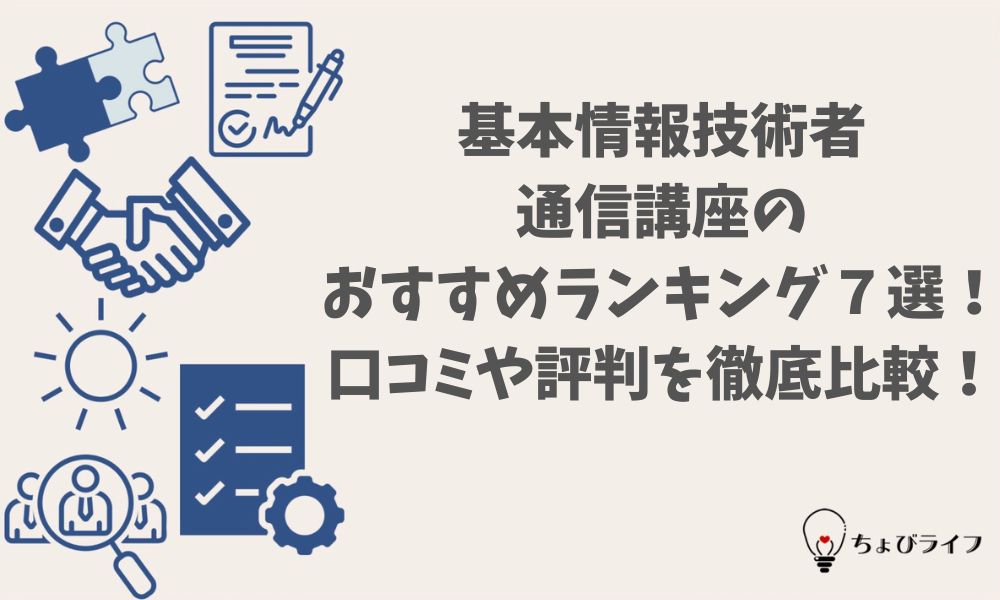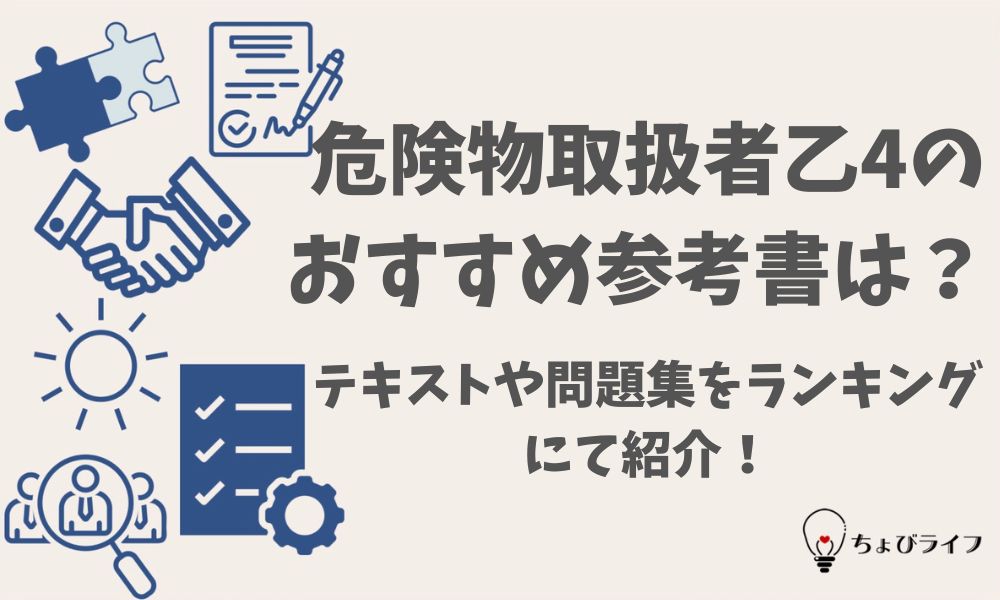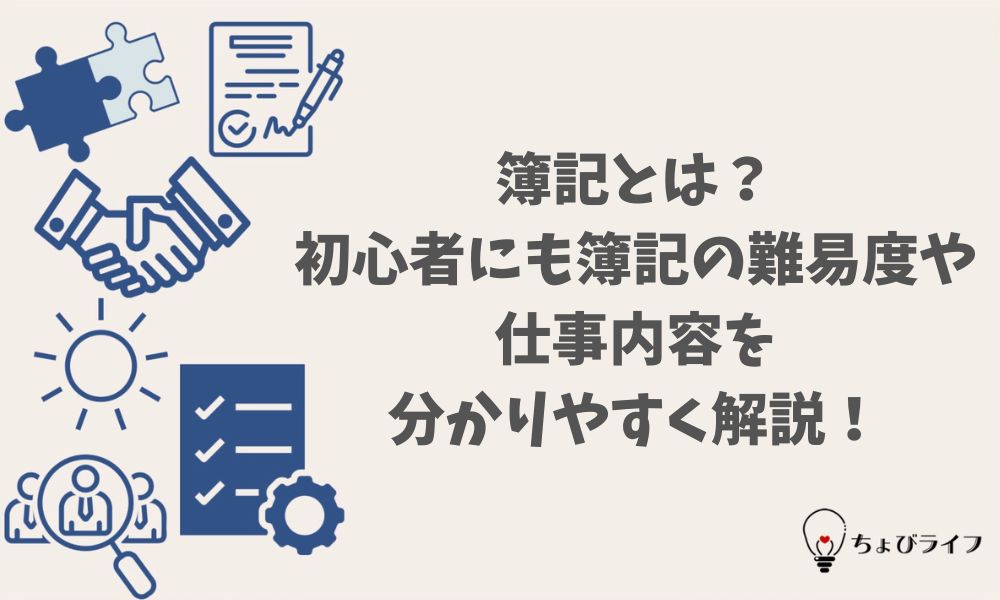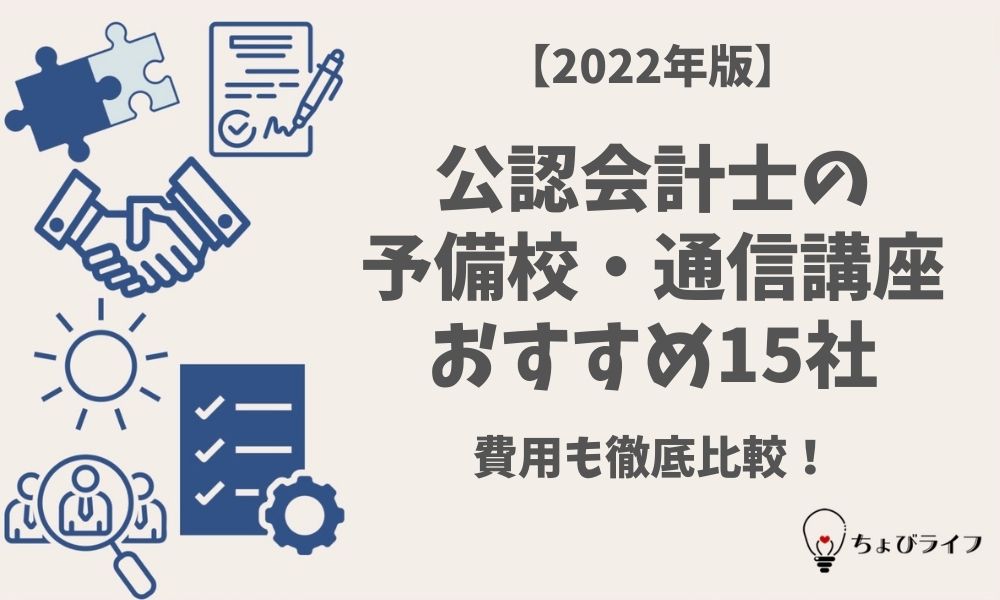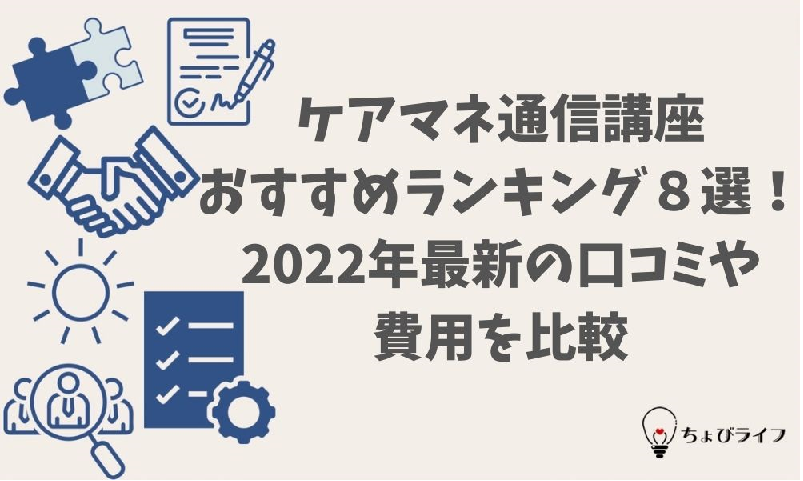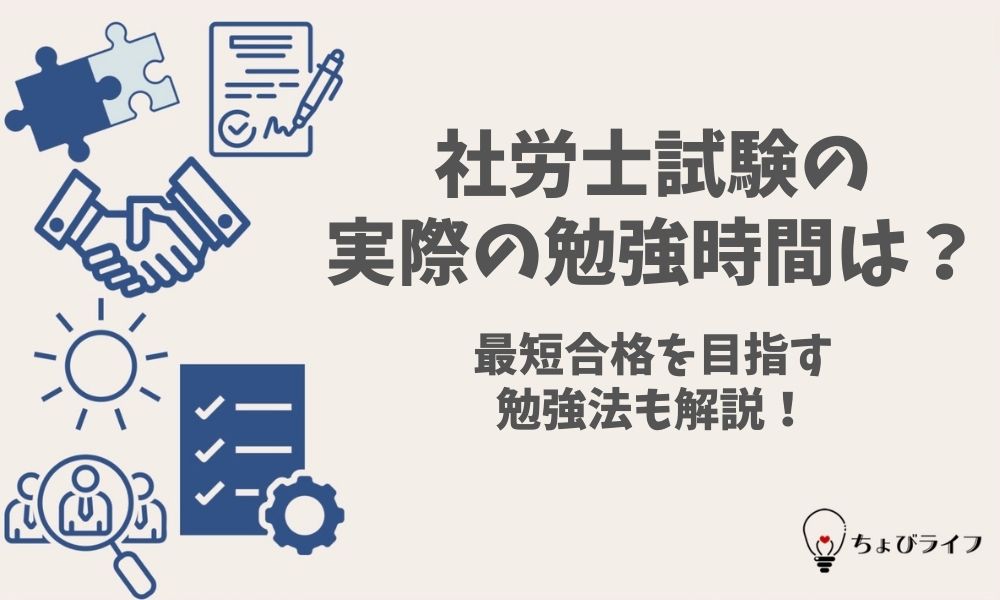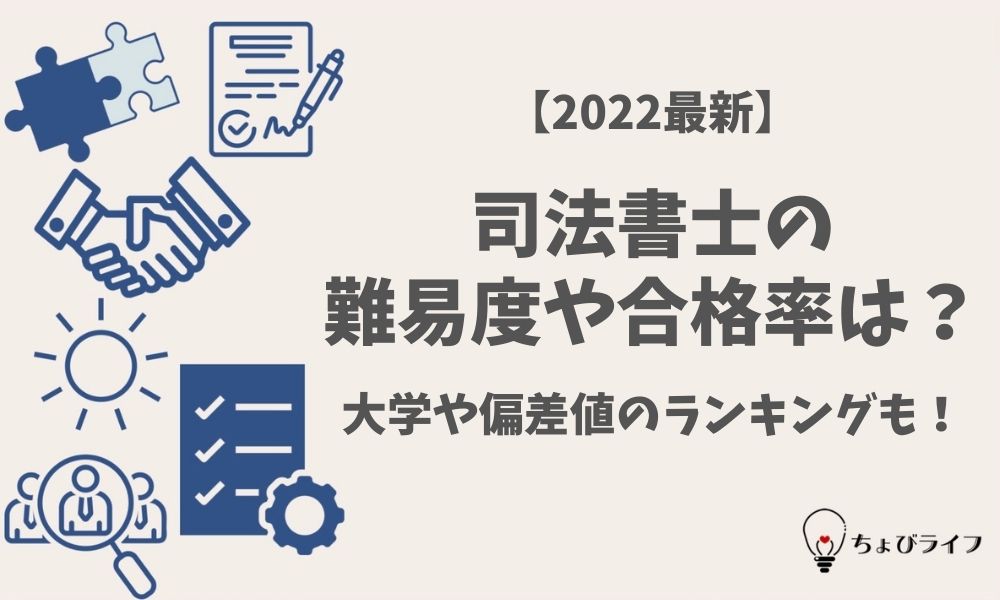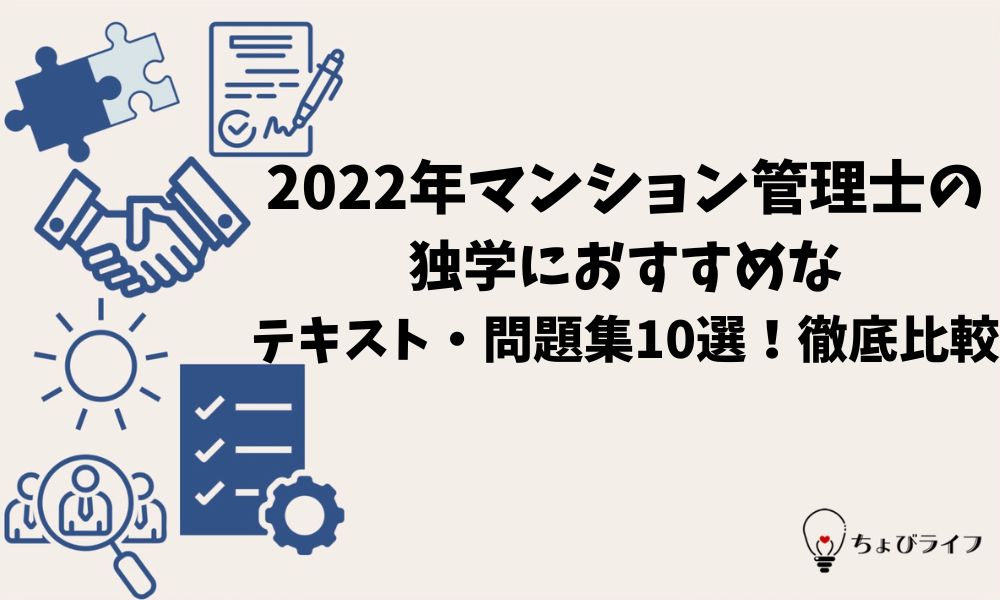二級建築士を目指しているけど実際独学で勉強するとなると、どういう勉強方法で何から始めたらいいの?いう方もいるのではないでしょうか。
「どういった勉強方法があるの?」
「独学でも合格できる勉強方法はあるの?」
「製図の試験はどんな試験なの?」
独学で二級建築士を目指している方の場合、勉強方法など色々な疑問をお持ちの方もおられると思います。
そんな疑問を解消できるよう、ここでは二級建築士を独学で目指す方のために勉強方法などをご紹介していきたいと思います。
また、独学で勉強している方にとっておすすめのテキスト・問題集はどういったものがあるのか気になりますよね。
二級建築士は、大変難易度の高い国家試験です。しかし、独学でも勉強方法を工夫し、コツコツと積み上げることで実際に合格している方もいます。
独学で二級建築士を学習する場合、少し工夫が必要なので、ここでは二級建築士の勉強方法や、おすすめのテキスト・問題集をご紹介していきますので、是非参考にしてみてください。
\おすすめテキスト・問題集/
二級建築士は独学でも合格できる?

まず最初に、二級建築士は独学でも合格を目指せます。
実際、独学で二級建築士を目指し合格されている方もいます。
しかし、二級建築士の試験は、学科試験と製図試験のどちらも合格しなければならず、独学では大変難しい試験であるといえます。
独学の場合、勉強方法に工夫が必要となりますのでその辺りも含め、以下で二級建築士試験について詳しく説明していきます。
二級建築士学科試験
まず、二級建築士の学科試験に関してですが、出題傾向が大きく変わることがなく毎年大きく変わりません。
そのため、学科試験の対策をしっかりとすることで、建築の専門知識がなくても合格を目指すことができます。
学科はテキストや過去問を繰り返し行うことで、高得点を目指せるという訳です。
次に、合格ラインは約60%なので、学科に関して100点満点中だいたい60点以上の正答率で合格することができます。
これは、100点満点中60点という低い基準であるため、ある程度のミスは許されます。
高得点を狙うとなると気負ってしまい勉強が辛くなるかもしれませんが、60点以上の得点であれば初学者でも合格を目指せますね。
しかし、独学で二級建築士を目指すといっても、難しいところもあります。
学科試験から製図試験までの期間が2か月しかないので学科試験の勉強だけでなく、製図試験の対策をしておかなければなりません。
製図は慣れないと大変難しいため独学では難しい面もあります。
独学であれば、添削をしてもらえないので自分で描く練習をして、添削までするとなると独学では難しいかもしれません。
ある程度、建築業界で実務経験があったり、建築の知識があると製図試験は合格しやすいでしょう。
学科は独学で学習し、製図はスクールや通信講座を利用するのもいいですね。
二級建築士受験資格
二級建築士の試験を受けるためには、受験資格があり、大学・短大・専門学校で指定科目を履修する必要があります。
指定科目とは、国土交通大臣の指定する建築に関する科目のことを指します。
建築関連の大学などを卒業している方でも、指定科目を所定の単位数履修しなければならないので注意が必要です。
二級建築士の指定科目は以下になります。
| 科目 | 単位数 |
| ①建築設計製図 | 3単位 |
| ②建築計画 | いずれか2単位 |
| ③建築環境工学 | |
| ④建築設備 | |
| ⑤構造力学 | いずれか3単位 |
| ⑥建築一般構造 | |
| ⑦建築材料 | |
| ⑧建築生産 | 1単位 |
| ⑨建築法規 | 1単位 |
| ①~⑨の合計 | 10単位 |
| ⑩複合・関連科目 | 適宜 |
| ①~⑩の合計 | 20単位 |
※参考:公益財団法人 建築技術教育普及センター (jaeic.or.jp) (2022年8月20日現在)
国土交通大臣の指定する建築に関する指定項目は、建築学科、デザイン学科、土木系の学科で履修することが可能です。
しかし、建築関係の学歴がない場合、指定科目を履修していなくても7年間の実務経験を積むことで受験資格を得ることができます。
この実務経験は、国土交通省が指定する建築に関する実務を行わなければなりません。
令和2年に建築士法が改正され、建築士試験の受験資格・免許登録要件が変わりました。
大学で指定学科を卒業すれば、実務経験がなくても受験可能になりました。
また建築に関する調査や、評価なども実務経験とみなされ実務経験として申告できるようになりました。
二級建築士試験の勉強時間
二級建築士合格に必要な時間は、だいたい500時間と言われています。
初学者であれば、1000時間の勉強時間が必要です。
働きながら、合格を目指す人にとって、500~1000時間という時間を確保し一人で勉強するのは大変かもしれません。
また、製図試験に関しては合格率が50%に対して、学科の合格率は30~40%台となっています。
これは、製図試験は試験日の3か月前に、試験課題を公表されることで合格率が50%と高い水準になっていると考えられます。
しかし、製図試験は難しいうえに、試験時間が5時間という長丁場で集中力も体力も必要とされます。
製図を攻略するにはやはり、何度もトレースの練習をすることです。
製図試験は5時間なので、その間にエスキスをスムーズに終わらせ、作図に取りかからなければなりません。
製図試験は、指定された設計条件に対しどのような図面を描くのかを攻略することで合格を目指すことができます。
独学で二級建築士を目指す場合、できるだけ早くから製図に取りかかり、本試験までに何度も描けるよう練習しておきましょう。
このように勉強方法を工夫することで初学者でも、合格を目指すことができます。
次項では、二級建築士の勉強時間について詳しく説明していきたいと思います。
必要な勉強時間の目安
建築や製図の知識によっても個人差があり、初めて勉強する人と経験者にもよって異なりますが、二級建築士はだいたい500時間くらいの学習時間が必要です。
ある程度の知識があれば、独学でも足りていない部分をテキストや過去問で補うことで500時間の学習で合格する方もいます。
ただ、初学者であればだいたい1000時間の勉強時間が必要だと言われています。
1000時間を勉強時間に換算すると、1年間で単純に計算しても1日3時間以上勉強する必要があります。
初学者の場合知識がないと、約1年間くらいの勉強時間は必要なので少しでも早く取りかかる方がいいですね。
3時間毎日勉強をするのは、働きながら独学で勉強する人にとってはかなり大変なことです。
働きながらであれば毎日勉強するのは難しい方も多いので、すき間時間を有効に使いましょう。
建築系の科目を履修した人であれば、設計製図に関して難しくないかもしれませんが、初学者だと独学では大変難しいでしょう。
設計製図だけ、独学ではなくスクールに通ったり通信講座を利用するのもいいですね。
独学で製図を練習する場合、平面図や、短計図、エスキスを毎日練習しコツコツと描いていくことで自信に繋がるので毎日2~5枚は描いていきましょう。
いずれにせよ、二級建築士を独学で勉強する方にとっては勉強方法を工夫し、長い挑戦になることを視野にいれておくといいですね。
おすすめの学習スタート時期
独学で2級建築士に合格するためには、いつ勉強を始めたらいいのか気になりますよね。
独学で勉強する場合の学習スタート時期を初学者の場合と、経験者の場合に分けてご紹介していきます。
初学者の場合、勉強時間は1000時間と言われています。
最初は、自分にあったテキストを購入し建築分野の用語に慣れていきましょう。
テキストを使って、建築用語や分からないことを調べながらの学習になります。
最初は、テキストを読んでいても難しくて分からないかもしれません。
しかし、初学者でも合格されている方もいますので安心してください。
1日3時間勉強したとしても1年はかかるので、1年前から準備を始めていきましょう。
忙しくて1年も前から準備をできないという方は、1日6時間の勉強時間を確保できる方なら半年前からのスタートでも間に合います。
本試験が7月にあるので、半年から1年じっくりと準備をしていけば、学科試験の勉強をしながら製図の準備を進めていけます。
経験者であっても500時間は必要なので、試験日を逆算すると1月から勉強をスタートしていきたいです。
12月に製図試験の合格発表があり、次年度の1月には新年度の過去問やテキストが販売されます。
ちょうど、半年の学習期間をみて1月には自分にあった問題集やテキストを購入し学習を始めていきましょう。
半年で合格を目指す場合
- 1月 学科試験開始
- 7月 学科試験 自己採点後製図勉強開始
- 9月 製図試験
1月から学習できるので、学科試験に時間をかけることができます。
しかし、中には独学で3ヶ月の勉強で合格されている方もいます。
3ヶ月で合格を目指す場合
- 4月 学科勉強開始
- 7月 学科試験 自己採点後製図勉強開始
- 9月 製図試験
3ヶ月で合格を目指す場合、4月から学習を始めていきます。
7月の学科試験までちょうど3か月しかないので集中して学習を進めていきましょう。
いずれにせよ、初学者でも経験者でも早く始める方が知識も定着し理解を深めていけます。
独学の場合、試験日を逆算してスケジュールを管理し学習を進めていくことで合格へ近づくでしょう。
\効率的に勉強できる通信講座がおすすめ/
二級建築士に独学で合格を目指すための勉強方法
二級建築士を独学で合格を目指すために、学習スケジュールを管理する必要があります。
また、勉強する際のポイントとして、次のポイントを抑えて勉強していきましょう。
独学で合格を目指すための勉強方法のポイント
- テキストと過去問のリピート学習
- 学科は法規から勉強する
- 製図試験の攻略
- 計画的な学習スケジュール
これらの勉強方法がポイントとなります。以下で詳しく説明していきたいと思います。
①テキストと過去問のリピート学習
学科試験の勉強はテキストと過去問を何度も繰り返しが学習することが重要です。
テキストは、市販のもので構わないので、自分好みのテキストを購入しましょう。
どうしても難しい用語などをイラストや図を使って分かりやすく説明してあるものを選ぶといいですね。
初学者の場合、建築用語や概念を勉強して全体像を把握していきます。
テキスト1回目
1度目は全体の流れを把握する感じで読み進めてみましょう。
最初は、分からないことが出てきても構いませんので、テキストの内容を読んで各項目の内容を意識しながら読み進めましょう。
見出しや太字などの重要ポイントを意識して、分からなくてもいいので気にせず読みましょう。
テキスト2回目
2度目は、分からないことを調べながら理解を深めていきます。
ここで、難しい用語など出てくると調べながらの学習になるので先に進まないことがあります。
書いてある内容をしっかりと時間をかけて読みこみます。
難しい用語や分からないことは、マーカーでチェックしたり付箋を貼っておくと、次に読んだ時に記憶に残りやすいのでやってみてください。
重点項目や、頻出問題などの出題箇所はしっかり熟読しましょう。
テキスト3回目
3度目は、理解したことを暗記するくらいの意識で読んでいきます。
自分の苦手な分野や項目はこの時点でできる限り解消していきましょう。
不得意な分野は再度、熟読していきます。
試験範囲が広く、なかなか覚えられないという方は、さらに4回、5回と繰り返し読み込みインプットしていきます。
そして、過去問をひたすら解くこともポイントです。
いきなり問題を解くのではなく、参考書などで問題を理解してから演習に取りかかるといいでしょう。
特に、「建築計画・建築構造・建築施工」は出題傾向が変わらないため、最低でも5年分の過去問を解きます。
過去問を解くことで、頻出問題も分かり試験内容が把握できるため正答率を上げることができるからです。
22013年以降から、過去問にない新傾向問題が出題されるようになりました。
新傾向問題が解けないことも予想して、それ以外の問題は必ず正解するようにしっかりと対策をしておきましょう。
過去問を繰り返すことで、頻出問題が分かり試験問題を解くことに慣れていきます。
本試験でも慌てないよう、何度も繰り返し過去問を解いていきましょう。
確実に、自分の得意分野では高得点を取り、苦手分野でも平均を取れれば合格に近づきますので繰り返し読む・繰り返し解くことをやってみてください。
こうやって何度も繰り返す勉強方法を行っているうちにしっかり知識が定着して、自信にも繋がりますのでおすすめです。
②学科は法規から勉強する
学科を勉強する際、一番最初は「法規」から勉強しましょう。
その理由は、学科試験でつまずきやすいのが法規だからです。
2級建築士試験では、法令集を持ち込むことができます。
法令集を持ち込めるため、できるだけ満点を取りたい分野になります。
法規とは、問題の選択肢の内容が正しいか、間違っているかを建築基準法が掲載された「法規集」で調べる問題となります。
必ず、法令集に答えがあるので過去問を解きながら、アンダーラインを引いたりして分かりやすくしていきましょう。
法令集はインデックスを貼っていても問題はありませんので、どんどん活用しましょう。
法令集に関しては、色々な種類が販売されているのでできるだけ自分にあった見やすいものを選びましょう。
問題に慣れるのはもちろんですが、法令集を使って検索スピードをあげたいので自分が調べやすい見やすい法令集で学習しましょう。
全てを暗記する必要はないので、問題文を読み法令集で間違い部分を探すといった一連の流れを素早く行う必要があります。
法規に慣れることで、点数も稼げるので検索スピードをあげ、インデックスシートを活用していきましょう。
また、法規を最初に勉強することで、学科の内容を全体的に把握することができます。
暗記の科目と違って一度法規の知識を身につけてしまえば時間がたっても忘れにくいです。
もし法規で満点を取れたら、他の項目で高得点が取れなくても合格できるため、法規を優先して勉強を始めましょう。
暗記の科目より身につけるのに時間がかかるため、法規を一番最初に学習し、理解を深めるために時間をかけて取り組んでいきましょう。
③製図試験の攻略
製図を描くことに慣れていない人は、まず模範解答をトレースして描くことに慣れる必要があります。
製図の経験がなくても、何枚もトレースで図面を描き、描き方を何度も練習し頭に入れることで慣れていきます。
何枚も描くことで、スピードアップにも繋がります。
また、課題の内容をしっかりと理解し、設計条件をもとに図面の計画をまとめましょう。
独学だと、難しいかもしれませんが、エスキスを練習し速く描けるようになると合格へ近づくことができます。
働きながら、独学で二級建築士を目指す方がどうしても不安な場合、製図だけスクールや通信講座を利用するのもおすすめです。
課題内容を詳しく解説してもらえ、エスキスのまとめ方を学ぶことができます。
また、模擬試験を受けることが出来たり講師による添削をしてもらえるので、レベルアップにも繋がります。
製図の試験対策は、本格的に製図を勉強したことがある人は描き方に慣れているかもしれません。
しかし、独学だと自ら添削し、1枚でも多くトレースで描いて課題をこなしていく必要があります。
また、課題の内容を理解しエスキスをまとめなければなりません。
自分の勉強方法では自信がなかったり、時間がない方、また、効率よく製図試験に取り組みたい方はスクールや通信講座もおすすめです。
④計画的な学習スケジュール
勉強の開始時期についてですが、計画的な学習スケジュールをたてることがポイントです。
まず、学科試験が7月上旬にあるので逆算しましょう。
二級建築士の大まかなスケジュールは以下の通りです。
- 3月上旬 試験スケジュールの詳細発表
- 4月上旬 受験申込書配布
- 4月中旬 受験申込受付開始
- 7月上旬 学科試験
- 8月下旬 学科試験合格発表
- 9月中旬 製図試験
- 12月上旬 製図試験合格発表
- 翌年1月 2級建築士免許受け取り
具体的にどの時期から勉強を開始するとよいのかは初学者と経験者でも異なりますが、7月の学科試験に向けて勉強を開始しましょう。
勉強は早めに始めるほうがいいのですが、初学者でも計画的に勉強をすることで効率よく学習することも可能です。
コツコツと勉強をすれば、独学でも合格を目指すことは可能です。
しかし、長期戦になってくるとモチベーション維持も難しくなります。
働きながら勉強する場合、通勤時間や休憩時間を使って学習をしたり、工夫しながら自分のペースで学習を進めていきましょう。
独学だと、一人で勉強するので難しい用語や分からないことが出てきたり不安な場合もあります。
テキスト片手に用語や難しいワードを調べながら勉強を進めていくのは時間もかかり、モチベーションを維持するのも非常に難しいです。
出来るだけ早めに学習を始めて、何月にはここまでのテキストを読み込むなど、具体的な目標を設定しながら進めていきましょう。
独学で合格を目指す場合、自分にあった勉強方法で計画的な学習スケジュールを組むことが大切になります。
\効率的に勉強できる通信講座がおすすめ/
二級建築士の学習スケジュールの立て方

二級建築士の試験は、学科試験と製図の試験に分かれています。
二級建築士に必要な情報を把握して、試験日を逆算してスケジュールをたてていくことがポイントです。
年度にもよりますが、だいたい以下の日程で行われます。
では、二級建築士試験について詳しく説明していきます。
試験概要
| 学科試験 | 7月の第一日曜日 |
| 製図試験 | 9月の第二日曜日 |
だいたい7月前半に学科試験が行われます。
学科の試験に合格しないと、製図試験を受験できないため確実に学科試験の対策をとる必要があります。
また、学科試験の2か月後に製図試験があるので、学科試験はしっかりと合格を目指していきましょう。
学科試験
| 科目 | 出題数 | 試験時間 |
| 学科Ⅰ(計画) | 25問 | 10:10~13:10(3時間) |
| 学科Ⅱ(法規) | 25問 | |
| 学科Ⅲ(構造) | 25問 | 14:20~17:20(3時間) |
| 学科Ⅳ(施工) | 25問 |
①出題数:全100問
②形式:5肢択一のマークシート形式
「学科Ⅱ」の法規の時間のみ法令集の持ち込みが可能。
製図試験
試験時間:11:00~16:00(5時間)
試験内容:課題に基づいた図面作成と計画の要点の記述
平行定規や三角定規なども持ち込み可能。
※課題は例年6月上旬に発表される
令和4年は6月8日に公表されており、設計課題は「保育所(木造)」です。
要求図面
- 1階平面図兼配置図【縮尺1/100】
- 各階平面図【縮尺1/100】
- 床伏図兼小屋伏図【縮尺1/100】
- 立面図【縮尺1/100】
- 短計図【縮尺1/100】
- 面積表
- 計画の要点など
試験問題を十分に読んだうえで、「設計製図の試験」に臨んでください。
また、設計与条件に対して解答の内容が不十分な場合、「設計条件・要求図面に対する重大な不適合」とみなされてしまいます。
少しのミスも許されないため、慎重に図面を描いていきましょう。
合格基準
学科試験の合格基準:4科目の100点満点中、合計60点以上の正答で合格
各科目及び総得点の合格基準点に達していること。
試験結果によっては、合格基準点に補正が入る場合もあります。
| 科目別配点 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
| 計画(25点) | 13点 | 13点 | 13点 | 14点 |
| 法規(25点) | 13点 | 13点 | 13点 | 13点 |
| 構造(25点) | 13点 | 13点 | 13点 | 13点 |
| 施工(25点) | 13点 | 13点 | 13点 | 13点 |
| 合計100点 | 60点 | 60点 | 60点 | 60点 |
令和3年、学科Ⅰ(計画)の合格基準点は14点に補正されました。
他の科目は13点が基準点で、合計点は60点で変更ありませんでした。
製図試験の合格基準:段階区分の最上位「ランクI」を獲得で合格
| ランク | 内容 |
| ランクⅠ | 「知識及び技能」を有するもの |
| ランクⅡ | 「知識及び技能」が不足しているもの |
| ランクⅢ | 「知識及び技能」が著しく不足しているもの |
| ランクⅣ | 設計条件・要求図面等に対する重大な不適合に該当するもの |
学科試験は、合格基準が60点を目指せばいいので、多少ミスをしても大丈夫でしょう。
しかし、製図に関しては「知識及び技能」を有するもの以外は不合格になってしまうため、大きなミスは許されない試験といえます。
合格率自体、学科試験も製図試験もそんなに高くないのですが、製図に関してはミスが許されないため特に注意が必要です。
\効率的に勉強できる通信講座がおすすめ/
二級建築士のおすすめテキスト・過去問・問題集

二級建築士を初学者が独学で目指す場合、テキスト選びは大変重要です。
そのため合格のために必要なテキストや過去問・問題集をご紹介していきます。
テキスト
- スタンダード 二級建築士2022年版
- 令和4年度版 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題
- 令和4年度版 2級建築士試験設計製図テキスト
過去問・問題集
- 令和4年度版 2級建築士試験学科過去問セレクト7Now&Next
- 2級建築士 分野別厳選問題500+100 令和4年度版
二級建築士のおすすめテキスト
「スタンダード 二級建築士2022年版」
出版社は建築士資格試験研究会で、価格は3,520円(税込)です。
このテキストはAmazonの星評価は星4.0で高評価です。
まず、このテキストの特徴として2色刷で見やすく、解答は別冊で使いやすくなりました。
学科試験4科目の復習と整理、過去問3年分がこの1冊でできるようになっています。
よく出題されるテーマを厳選してあり、見開き構成で、項目別に解説してあります。
基本に沿って学習できるので、安心ですね。
また、出題された重要語句や内容すべてが初歩から基本を学べるように詳しく解説してあります。
毎年、定評があり、初歩から学べ理解力をアップできるおすすめのテキストです。
このテキストは2022年度版で最新のため、口コミが見つかりませんでした。
同じスタンダードのテキストで、2019年度版、2021年度版の口コミをご紹介します。


このテキストは要点を分かりやすくまとめてあります。
しかし、口コミでは問題集を解いている方が時間を有効に活用できるとありますが、やはり独学で二級建築士を学ぶ方にテキストは必要です。
このテキストは初歩から基礎を学べるように詳しく解説されていて、基本が学ぶことができますので是非参考にしてみてください。
次に紹介するのは、「令和4年度版 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題」です。
「令和4年度版 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題」
出版社は総合資格、価格は3,630円(税込)です。
このテキストはAmazonの星評価は星4.0で高評価です。
このテキストは、必要な知識を体系的に理解できるように工夫してあります。
試験に必要な知識をコンパクトにまとめ「重要ポイント編」を掲載し、その後「確認問題」を行うことで知識のアウトプット・定着をはかります。
また、各問題には取り組んだ際の理解度をチェックできるようになっており、効率よく学習を進めることができます。
また、過去10年分の出題分類表も掲載されていて、年度ごとの出題項目と出題数が一目でわかるのでおすすめのテキストです。
では、このテキストの口コミを紹介します。


以上、口コミをご紹介しました。
口コミにもあるように、イラストが少ないので難しく感じる方もいるかもしれません。
しかし、このテキストは重要ポイントをしっかり抑えてあり、試験に必要な重要な内容を網羅されているので是非参考にしてみてください。
最後に、「令和4年度版 2級建築士試験設計製図テキスト」をご紹介します。
 引用元:Amazon
引用元:Amazon「令和4年度版 2級建築士試験設計製図テキスト」
出版社は総合資格、価格は4,180円(税込)です。
このテキストはAmazonの星評価で3.5と高評価です。
このテキストは、設計製図のテキストで現行の試験制度に対応したチャレンジ課題3点が収録してあります。
エスキスの考え方を初学者でも分かりやすく、線の引き方や線の種類といった基礎から、平面図や短計図などの必須図面の描き方まで解説しています。
木造・RC造・S造の3つの構造種別の図面も解説してあります。
また、4色フルカラーなので図面が見やすく理解しやすいテキストになっています。
では、このテキストの口コミを紹介します。


二級建築士のおすすめ過去問・問題集
二級建築士の試験に独学で目指す場合、テキストも重要ですが、過去問・問題集も大変重要です。
テキストだけでは、試験の内容が具体的に分からないため、過去問・問題集も1冊は購入しましょう。
では、二級建築士の過去問・問題集を紹介していきます。

「2級建築士 分野別厳選問題500+100 令和4年度版」
出版社は日建学、価格は2,970円(税込)です。
このテキストはAmazonの星評価で星5.0と高評価です。
この問題集は、分野別に厳選された問題を500+100問掲載されています。
過去問から合格に必要な問題を厳選してあるのでポイント整理や確認にも役立てます。
重要ポイントは要点を学習でき確認問題で理解度をチェックできるので是非、参考にしてみてください。
この問題集は令和4年度版で最新のもので、口コミが見つかりませんでした。
「2級建築士分野別厳選問題500+100」問題集の令和3年度版の口コミをご紹介します。

\効率的に勉強できる通信講座がおすすめ/
二級建築士を独学で勉強するメリット・デメリット
二級建築士は独学でも合格を目指せます。
しかし、独学の場合メリットとデメリットがあるので注意が必要です。
また、独学の場合は製図試験を一人で勉強しないといけないため、十分な対策が必要です。
以下で、二級建築士を独学で勉強するメリットとデメリットを説明します。
独学で勉強するメリット
独学で勉強するメリットとして、まず一番は自分の好きな時間に好きな場所で勉強できるので、自分のペースで学習を進めることができます。
働きながら、二級建築士を目指している方にとって、決まった時間にスクールに通うのは難しいでしょう。
その点、独学の場合は働きながらでも、すき間時間を利用して勉強することができます。
通勤時間や休憩時間、仕事が休みの日に好きな場所で勉強することもできます。
縛られることがないので、自分のペースで勉強を進めていけるのは働きながら二級建築士を目指している方にとってメリットになります。
次に、独学だとテキストや過去問などを何冊か購入したとしても、それほどの高い金額ではありません。
スクールや通信講座を利用すると、高い授業料などの学費を払わなくても良いので大きなメリットといえます。
学科試験に関しては、テキストを読み込み、何度も過去問を繰り返し解くことで合格は可能です。
二級建築士のテキストや問題集を何冊か買っても、授業料ほどのお金はかかりませんので何冊か購入するのもいいでしょう。
また、過去3年分の過去問は、公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページで公開されています。
誰でも閲覧することができるので、是非参考にしてみてください。
独学で勉強するデメリット
次に独学で勉強する場合、自分のペースで学習できる反面、メリットもあります。
分からないことがあってもすぐに誰かに質問することができないので、自分で調べながらの学習になります。
身近に詳しい人がいたら聞くこともできますが、学校の先生のように気軽に質問するのは難しいでしょう。
また、一人で勉強していると孤独感が強くなります。
気軽に相談することもできないと、不安なまま学習を進めていくことになります。
特に製図試験の対策が難しく、製図に関してはスクールを利用したり通信講座を使うのもいいでしょう。
また、500~1000時間という長時間の勉強時間が必要となるため、モチベーションの維持が難しいです。
働きながら、半年から1年の長期戦で独学で学習するのは、相当頑張らないとモチベーション維持ができないでしょう。
上手にスケジュール管理を行いながら、挫折しないよう学習を進んていきましょう。
長期戦で考えると、モチベーション維持が難しくても、毎日テキストを読むなどルーティーンにしてみてください。
勉強することを習慣化してしまえば、知識も定着し理解も深まるので毎日コツコツと取り組みましょう。
それ以外にも、建築関係の学校を卒業しておらず7年以上の実務経験が必要になります。
実務経験もない場合は、所定の講座を受ける必要がありますので、通信などを利用するのもいいでしょう。
独学で二級建築士を目指す場合、デメリットを補えるのが通信講座となります。
以下でおすすめの通信講座を紹介していきます。
独学が心配・不安なら
\効率的に勉強できる通信講座がおすすめ/
建築士のおすすめ通信講座
二級建築士を独学で勉強する場合、不安なこともでてくるでしょう。
その不安な部分を補ってくれるのが通信講座になります。
また、働きながら学習することは大変難しく、効率よく学習するために通信講座を利用するのもおすすめです。
通信講座は、勉強方法が分からない方や、時間がなくて勉強がはかどらない方にも効率よく学習できます。
ここではおすすめの通信講座「スタディング」を紹介していきます。
スタディングでは、特に働きながら勉強する方にとってすき間時間を利用しながら学習を進めていけます。
以下で詳しく説明します。
スタディング

引用元:スタディング
| 講座名 | 2級建築士学科・製図総合コース 【2023年合格目標】 |
| 料金 | 一括88,000円(税込)
分割の場合月々7,500円×12回から |
| 教材/テキスト |
|
| サポート体制 |
|
| 詳細 | ▶︎詳細は公式サイトでご確認ください |
(2022年8月16日現在)
スタディングの2級建築士学科・製図総合コースでは学科から製図対策まで、合格ノウハウを凝縮した総合コースになっています。
学科は高得点ではなく、合格点を目指し効率的に学習カリキュラムを構築してあります。
過去問の分析をし、必要な部分を丁寧に学習し、合格に必要ない部分はそぎ落とすメリハリ学習で合格を目指せますね。
製図に関しては、速く描くための手順やテクニックをしっかりと学び、エスキス法により膨大な課題をこなしていきます。
初めて学ぶ人にとって、分かりやすい講義で基礎から着実に楽しく学習できるのではないでしょうか。
紙のテキストではないので、スライドの図表が講義の説明に合わせて動き、制度の仕組みや切り替わりもビジュアル的に分かりやすくなっています。
このWEBテキストはフルカラーで図表も分かりやすさを追求したテキストになっているので安心ですね。
動画講義も、難しいところを中心に詳しく説明してあるので、WEBテキストは、知識の整理に効果的に使えます。
働く人にとっては、通勤時間などのすき間時間を使って学習できるので効率的ですね。
また、製図に関して速く描く手法をビデオや音声を使って解説してくれています。
時間内に描ききれないということがないよう、基本から、手順をアニメーションを多用したスライドで説明しています。
製図が苦手という方も分かりやすく説明されているので安心して学ぶことができるでしょう。
スタディングでは、様々なサポート体制があり中でもAIを使った復習機能サービスが使えます。
AIが復習するタイミングに自動で出題してくれるので効率的に実力をアップすることができます。
また、前回間違えた問題なども復習できるので知識の定着がしやすいです。
独学で学習する場合、一人ではなかなか進まないこともありますが、AIによるサポートを受けられるので学習意欲にも繋がりますね。
また、スタディングは全てマルチデバイス対応なので、外出時にはスマートフォン、自宅ではPCなど学習スタイルを自由に選べます。
講義はもちろんのこと、WEBテキストもスマート問題集も全てマルチデバイスで対応しています。
講義をダウンロードしておけば、WI-FIがなくてもオフラインで学習することが可能なので、通勤時間や休憩時間でも安心ですね。
そして、苦手分野を徹底攻略するために、スマート問題集・セレクト過去問集があります。
これは、間違えた問題など苦手な分野を繰り返し集中して練習することができます。
また、自分が行った学習の平均点が表示されるので自分の実力を確認することもできます。
また、学習状況を可視化することで自分がどれくらい学習したのか進捗状況が数値で見えるようになります。
毎日の学習がグラフ化されることでモチベーションアップに繋がり、学習の習慣化に役立つのではないでしょうか。
最後に、独学では仲間と情報を共有することが難しいですが、スタディングでは勉強仲間機能というのがあります。
全国の仲間と学習内容を共有できることで、一人で勉強している不安感もなくなるでしょう。
また、同じ目標に向かっているからこそ励ましたり、刺激をうけるので合格への道へ前進できそうです。
以上、スタディングの通信講座をご紹介しました。
現在スタディングでは、オンラインで無料の講座を受けられるので是非参考にしてみてください。
まとめ
今回、2級建築士を独学で勉強する方にどういう勉強方法があるのか、また、おすすめのテキストや問題集をご紹介しました。
どの学習でもいえますが、試験までにいかに早くから勉強に取りかかり、知識を定着し理解を深めるかで合格へ近づくことができます。
社会人の場合、忙しくて時間がない方も勉強方法を工夫して合格を目指していきましょう。
500~1000時間の学習は長期戦になります。
働きながら、モチベーションを維持しながらの学習は大変難しいです。
ただ、出題傾向がある程度決まっていることから、徹底的に過去問を繰り返し行うことで合格を目指すことは可能です。
特に製図に関しては、初学者の場合難しいので通信講座などを利用するのもおすすめです。
途中で、難しいなと感じたら通信講座などを利用していきましょう。
効率よく学習し、勉強方法を工夫して2級建築士に合格に近づくことができます。
これから、ますます活躍できる資格ですので是非取得を目指してください。
\効率的に勉強できる通信講座がおすすめ/
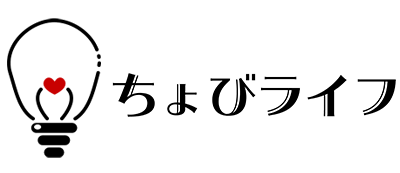
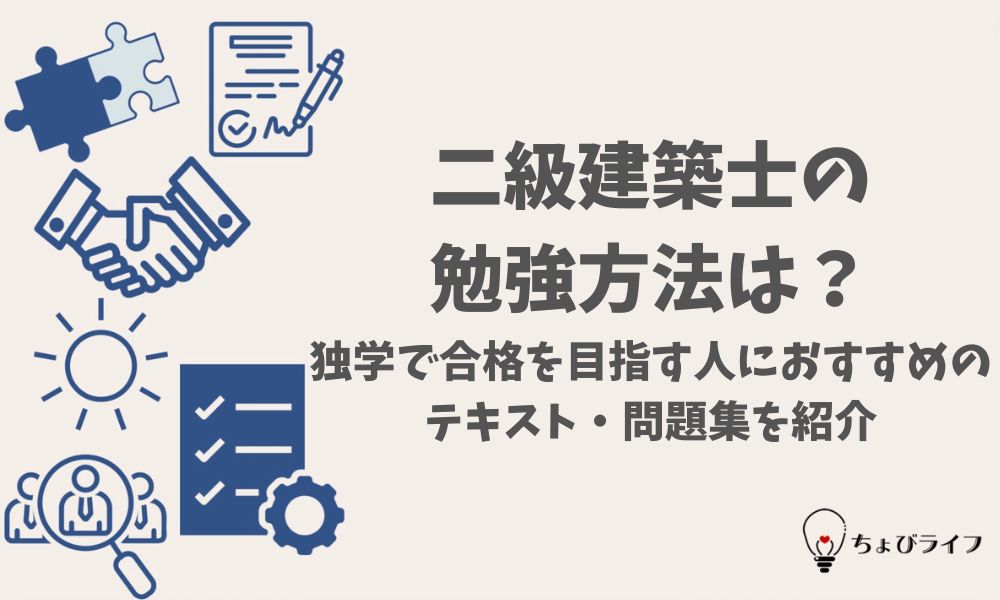

 引用元:
引用元: 引用元:
引用元: